- 簿記を勉強していたら固定資産を売買する取引が出てきたんだけど……
- 固定資産を取得するのにかかる費用の処理方法が分からない
- 固定資産の仕訳について教えて!
固定資産の仕訳は減価償却も複雑に関係してくるので、難しいと感じる人が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん固定資産の購入の仕訳についても売却の仕訳についても熟知しています。
この記事では簿記3級の合格に必要な固定資産の購入の仕訳と売却の仕訳について解説します。
この記事を読めば固定資産の購入と売却の仕訳が理解できます。簿記3級の試験でも自信を持って解答できるようになります。
結論を言うと、固定資産を購入したときには固定資産の購入代金と付随費用を合わせて固定資産の勘定科目(建物や備品など)で処理します。
固定資産を売却したときには、その固定資産に関する残高を全て消去し、貸借差額は固定資産売却損益として処理します。
固定資産:企業が1年を超えて使用する資産

企業が営業のために1年を超えて使う建物や備品、車両運搬具、土地などを固定資産といいます。「1年を超えて」というところがポイントです。1年以内に使い切ってしまうものは消耗品となります。
以下、具体的に固定資産を見ていきましょう。
建物
営業用の店舗や事務所、倉庫などが当てはまります。付随費用としては、不動産取得税や仲介手数料などがあります。
備品
営業用の机、イス、パソコンなどが当てはまります。付随費用としては、送料や据付費などがあります。
車両運搬具
営業車やトラックなどが当てはまります。付随費用としては自動車取得税などがあります。
土地
駐車場などが当てはまります。もちろん建物を土地つきで持っている場合も当てはまります。付随費用としては不動産取得税や仲介手数料などがあります。
固定資産の取得原価=購入代金+付随費用

固定資産を取得した場合、取得原価は購入代金に付随費用を足した金額になります。取得原価=購入代金+付随費用ということです。
有価証券 、仕入諸掛の場合と考え方は同じです。固定資産の付随費用は、その固定資産を取得してから使えるようにするまでにかかった費用と考えて大丈夫です。
固定資産の購入時の仕訳

土地の購入
営業用の土地を購入し、代金8,000,000円、不動産取得税100,000円、仲介手数料80,000円、登記料70,000円を小切手を振り出して支払った。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
全て足したら8,250,000円です。8,250,000円を全て小切手を振り出して支払っているので『(貸)当座預金8,250,000』となります。
問題は借方です。取得原価に何が含まれるのかがポイントです。
土地代金は当然として、不動産取得税も仲介手数料も登記料も全て取得原価に含めます。
土地は資産なので、資産の増加は借方に記入します。というわけで『(借)土地8,250,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 8,250,000 | 当座預金 | 8,250,000 |
建物の購入
営業用の建物を購入し、代金6,000,000円、不動産取得税50,000円、仲介手数料60,000円、登記料90,000円を小切手を振り出して支払った。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
全て足したら6,200,000円です。6,200,000円を全て小切手を振り出して支払っているので『(貸)当座預金6,200,000』となります。
不動産取得税も仲介手数料も登記料も全て取得原価に含めるのは土地の場合と同じです。
建物は資産なので、資産の増加は借方に記入します。というわけで『(借)建物6,200,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 6,200,000 | 当座預金 | 6,200,000 |
備品の購入
パソコン400,000円を購入し、運送費および据付費40,000円とともに月末に支払うことにした。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
運送費はパソコンを使えるようにするための費用と考えられるので付随費用です。取得原価に含めます。パソコンは備品です。
備品は資産なので、資産の増加は借方に記入します。というわけで『(借)備品440,000』となります。
月末に支払うことにしたので、未払金で処理します。未払金は負債です。負債の増加は貸方なので『(貸)未払金440,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 440,000 | 未払金 | 440,000 |
うっかり貸方を買掛金で処理しないようにしなければいけません。このパソコンは商品として仕入れているわけではないので買掛金では間違いとなります。
固定資産(土地)の売却

土地の売却(帳簿価額より高く売った場合)
帳簿価額400,000円の土地を500,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした。
この例題の仕訳について考えてみます。
この土地は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。よって、帳簿価額を貸方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。『(貸)土地400,000』となります。
また、500,000円を月末で受け取るので『(借)未収金500,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを500,000円で売ることができたということは、この差額100,000円は収益です。100,000円儲かったと考えられます。
この収益は固定資産売却益という収益の勘定科目を使って表します。よって『(貸)固定資産売却益100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 | 500,000 | 土地 固定資産売却益 | 400,000 100,000 |
土地の売却(帳簿価額より安く売った場合)
帳簿価額400,000円の土地を300,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした。
この例題の仕訳について考えてみます。
この土地は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。よって帳簿価額を貸方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。『(貸)土地400,000』となります。
また、300,000円を月末で受け取るので『(借)未収金300,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを300,000円で売ったということは、この差額100,000円は損失です。100,000円損したと考えられます。
この損失は固定資産売却損という費用の勘定科目を使って表します。よって『(借)固定資産売却損100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 固定資産売却損 | 300,000 100,000 | 建物 | 400,000 |
固定資産の売却(直接法)

建物の場合は土地と違って減価償却を行っています。そのため売却の仕訳は複雑になります。
必要がなくなった固定資産を売却したときは、その固定資産を帳簿から減らす仕訳を切ります。
直接法では固定資産の金額は帳簿価額を表しています。帳簿価額を帳簿から減らすことになります。
固定資産の売却の仕訳を理解するためには減価償却の理解が不可欠です。減価償却については「【簿記】減価償却」で詳しく解説しています。
固定資産の売却(直接法)の仕訳
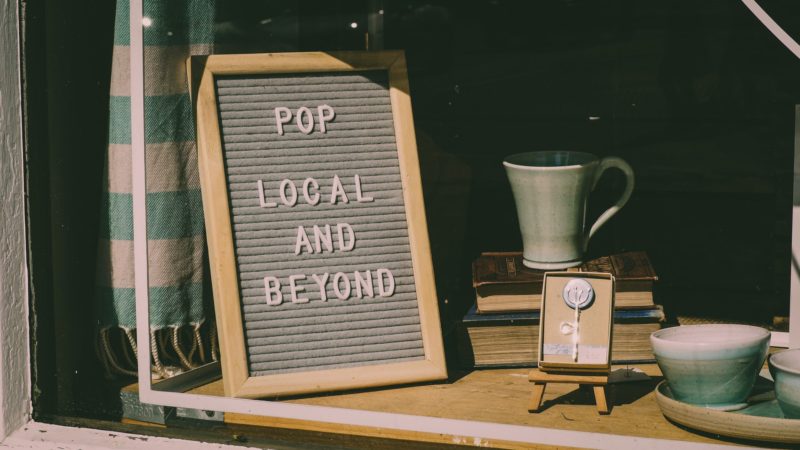
建物の売却(帳簿価額より高く売った場合)
帳簿価額400,000円(取得原価1,000,000円、減価償却累計額600,000円)の建物を500,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした(直接法)。
この例題の仕訳について考えてみます。
この建物は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。直接法で記帳されているので、帳簿の借方の金額は帳簿価額です。
よって、帳簿価額を貸方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。『(貸)建物400,000』となります。
また、500,000円を月末で受け取るので『(借)未収金500,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを500,000円で売ることができたということは、この差額100,000円は収益です。100,000円儲かったと考えられます。
この収益は固定資産売却益という収益の勘定科目を使って表します。よって『(貸)固定資産売却益100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 | 500,000 | 建物 固定資産売却益 | 400,000 100,000 |
建物の売却(帳簿価額より安く売った場合)
帳簿価額400,000円(取得原価1,000,000円、減価償却累計額600,000円)の建物を300,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした(直接法)。
この例題の仕訳について考えてみます。
この建物は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。直接法で記帳されているので、帳簿の借方の金額は帳簿価額です。
よって帳簿価額を貸方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。『(貸)建物400,000』となります。
また、300,000円を月末で受け取るので『(借)未収金300,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを300,000円で売ったということは、この差額100,000円は損失です。100,000円損したと考えられます。
この損失は固定資産売却損という費用の勘定科目を使って表します。よって『(借)固定資産売却損100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 固定資産売却損 | 300,000 100,000 | 建物 | 400,000 |
固定資産の売却(間接法)

必要がなくなった固定資産を売却したときは、その固定資産を帳簿から減らす仕訳を切ります。帳簿価額を帳簿から減らせばいいということです。
間接法では固定資産の金額は取得原価を表し、減価償却累計額は過去の減価償却費の合計を表しています。
『帳簿価額=取得原価-減価償却累計額』なので、帳簿価額を帳簿から減らすためには、取得原価と減価償却累計額を両方とも減らさなければなりません。
固定資産の売却(間接法)の仕訳

建物の売却(帳簿価額より高く売った場合)
帳簿価額400,000円(取得原価1,000,000円、減価償却累計額600,000円)の建物を500,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした(間接法)。
この例題の仕訳について考えてみます。
この建物は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。間接法で記帳されているので、帳簿の借方には取得原価、貸方には減価償却累計額が記帳されています。
そこで、取得原価を貸方に、減価償却累計額を借方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。『(貸)建物1,000,000』『(借)減価償却累計額600,000』となります。
また、500,000円を月末で受け取るので『(借)未収金500,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを500,000円で売ることができたということは、この差額100,000円は収益です。100,000円儲かったと考えられます。
この収益は固定資産売却益という収益の勘定科目を使って表します。よって『(貸)固定資産売却益100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却累計額 未収金 | 600,000 500,000 | 建物 固定資産売却益 | 1,000,000 100,000 |
建物の売却(帳簿価額より安く売った場合)
帳簿価額400,000円(取得原価1,000,000円、減価償却累計額600,000円)の建物を300,000円で期首に売却し、代金は月末に受け取ることにした(間接法)。
この例題の仕訳について考えてみます。
この建物は売却と同時になくなるので、帳簿からもなくしてしまわなければなりません。間接法で記帳されているので、帳簿の借方には取得原価、貸方には減価償却累計額が記帳されています。
そこで、取得原価を貸方に、減価償却累計額を借方に記入して、帳簿からなくしてしまいます。よって『(貸)建物1,000,000』『(借)減価償却累計額600,000』となります。
また、300,000円を月末で受け取るので『(借)未収金300,000』です。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、借方と貸方の差額は何を意味しているのでしょうか。
帳簿価額が400,000円のものを300,000円で売ったということは、この差額100,000円は損失です。100,000円損したと考えられます。
この損失は固定資産売却損という費用の勘定科目を使って表します。よって『(借)固定資産売却損100,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却累計額 未収金 固定資産売却損 | 600,000 300,000 100,000 | 建物 | 1,000,000 |
【まとめ】固定資産(土地・建物など)の取得と売却の仕訳

固定資産を購入したときには固定資産の購入代金と付随費用を合わせて固定資産の勘定科目(建物や備品など)で処理します。
付随費用とは固定資産を取得してから使えるようにするまでにかかった費用です。
固定資産を売却したときには、その固定資産に関する残高を全て消去し、貸借差額は固定資産売却損益として処理します。
- 弊社が運営している【簿記革命3級】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座-簿記3級」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに簿記3級の合格を目指して勉強したい方は簿記3級通信講座【簿記革命3級】をご検討ください。
- 簿記3級を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記3級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法-簿記3級」で詳しく解説しています。
- 簿記3級の独学に向いたテキストについては「【2021年版】独学向け簿記3級おすすめテキスト【9つのテキストを徹底比較】」で詳しく解説しています。


コメント
簿記の勉強をしていて、土地の取得に関して、伺いたいことがあります。
条件: ・建物仮勘定 55,700,000
・建物仮勘定の構成内訳
1.建物付土地購入代金 24,400,000
2.建物除去費用 3,000,000
3.建物廃材売却収入 △1,500,000
4.土壌入替費用 5,000,000
5.整地費用 1,800,000
6.建物設計費用 1,200,000
7.建物建設費用 21,300,000
8.落成式典費用 500,000
・新たな事業所設置のために、工場建物付土地を購入し建物を建設。後に地質調査
を行い、薬品反応があったため現状のまま使用することは困難であり、工場建物
取り壊しの後、土壌入替を行った。
問題の要旨は、建物仮勘定金額を土地、建物、修繕費、その他費用に適切に割り振ること
ですが、僕が疑問とするのは、建物除去費用と土壌入替費用の峻別についてです。
「土地の原状回復費用」について、僕は「自分が土地を使用できる状態にするまでに要した費用」と解釈して、建物除去費用、土壌入替費用ともに土地の取得原価に加算しました。
しかし、土壌入替費用は修繕費として取り扱うようです。調べたところ、法施令132の資本的支出の要件に該当しない等ということが考えられたのですが、どうも腑に落ちません。
僕の中では、土地の原状回復=自分が使用可能な状態まで戻す、と解釈してしまっているのですが、その解釈では建物除去費用と土壌入替費用の明確な峻別が難しいです。どのように解釈すれば良いでしょうか。
また、修繕費とするか取得原価とするか、国税通達等によって慣習的な区分はある程度
なされているようですが、理論的・学問的な判断基準等は存在するのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。取得原価に算入するかどうかは個別で判断するもので、理論的・学問的な判断基準がありません(具体的に国税庁に問い合わせることも多いところです)。明確な判断基準ではなく、あくまでも私の考えとしてお伝えします。
「土地の原状回復」についての私の考えはしうちんさんと概ね同じです。少しだけ付け加えたいところがあるので、次の通達を引用します。
・法人税基本通達7-3-7(事後的に支出する費用)一部抜粋
減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとする(中略)当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。
つまり、「取得後の付随費用は取得原価に算入しないことができる」「当初から支出が分かっていた場合は取得原価に算入する」ということです。
「予測できなかった付随費用が後から出てきたときにそれを取得原価に算入しなければならない」というルールにすると、会計処理が煩雑になるため、そういった事態を避けるための通達だと解釈しています(追記:固定資産の取得原価を過少にしないためという目的の方が大きそうです)。
この通達から考えると、「土壌入替費用」が必要になると前もって分かっていたのかが争点になりそうです。取壊や整地は予測できそうですが、土壌入替は予測できないように思えます。そこで、土壌入替は取得原価に算入しないのではないかというのが私の意見です。
正確なところは私もよく分かりません。もしこの問題が本試験で出題されていたら、私も土壌入替費用を取得原価に算入していた可能性が高いです。あくまでも参考程度に読まれてください。
※ちなみに、「取得後おおむね1年以内に取壊しに着手した場合」は「最初は取り壊すつもりはなかった(最初は購入した建物をそのまま使うつもりだった)」という説明は通りません。初めから取り壊すつもりだったとみなされます。そのため、取壊や整地は予測できたとみなされます。
回答ありがとうございます。
質問の内容が煩雑となってしまい、申し訳ありませんでした。
・会計処理上、修繕費としても取得原価としても誤りではないが、修繕費とするのが実務上
は望ましい、と理解しました。この設定条件の場合、やはり建物付土地取得の後、土壌
改良の必要性が生じたという時系列が重要だと考えるべきなのでしょうか。
・実際、土地購入の後に土地が汚染されていたと気づくケースは考えにくいですが、売買
契約上、土地改良を買手に任せる場合、買手負担の土地改良費用は土地の取得原価に
含める場合があることや、そもそも土地の購入価格に、売手が行った土地改良費用が
含まれている場合を考えると、さらに混乱しそうです。
土地の取得だけでも様々な考え方がありとても面白いですが、問題を解く際には少々面倒
くさいですね。今回も丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。
コメントありがとうございます。
>会計処理上、修繕費としても取得原価としても誤りではないが、修繕費とするのが実務上は望ましい
修繕費とした方が直近の納税額が少なくなるので、企業としては修繕費としたい、逆に税務署としてはできるだけ取得原価に算入してほしいという綱引きがあります。企業の立場からは修繕費が望ましいです。
>この設定条件の場合、やはり建物付土地取得の後、土壌改良の必要性が生じたという時系列が重要だと考えるべきなのでしょうか。
最初から土壌改良が必要だと分かっていたのか、そうでないのかが最重要だと思います。最初から土壌改良が必要だと分かっていたのであれば、その分「建物付き土地」の値段が安くなっているはずです。にも関わらず土壌改良費用を修繕費(費用)とすることが認められると土壌改良費用の金額だけ取得原価を不正に下げることができてしまいます。「法人税基本通達7-3-7(事後的に支出する費用)」にはそういった不正を防止する目的もあります。
>実際、土地購入の後に土地が汚染されていたと気づくケースは考えにくいですが、売買契約上、土地改良を買手に任せる場合、買手負担の土地改良費用は土地の取得原価に含める場合があることや、そもそも土地の購入価格に、売手が行った土地改良費用が含まれている場合を考えると、さらに混乱しそうです。
本当にそのとおりです。
複雑になりすぎるので前回の回答では触れなかったのですが、法律上、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)というものがあり、土地や建物に瑕疵(欠陥)があった場合は瑕疵を知ったときから1年以内に売主に通知すれば「土壌入替費用」を売主に請求することができます。
この請求を行っていれば土壌入替費用は当社の費用とはなりません。逆に言うと、当社の費用となっているということは購入して最低でも1年以上たっていることになります。1年以上たっているのであれば、「建物付土地の取得」と「建物除去以降の取引」は別の取引と考え、「建物除去以降の取引」については「資本的支出なのか修繕費なのか」という判断で行っていくことになります。
この解釈で問題を解けば、土地改良費用は修繕費となります。ちなみに、建物解体費用は撤去目的なら「固定資産除却損」、建て替えが目的なら「資本的支出(固定資産)」になるので、この場合は固定資産となります。
もしかしたらこの解釈で解くべき問題だったかもしれません(問題文に契約不適合責任について全く記述がなかったので前回の私の回答では購入から1年以内に建物除去などに着手したとみなしました)。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
連投になり申し訳ありません。
土壌入替に要した費用を修繕費とすることが気になって色々考えたのですが、
「修理改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産の原状回復に要した金額は修繕費に該当する(法基通7-8-2)。」との
記載を見つけ、確認したいことがあります。
薬品反応があったということは、土地は毀損しており、土壌入替による土地の原状回復が
必要だった。対して建物除去費用は、土地の毀損とは無関係であり、土地の原状回復には
当たらない。
上記のような解釈であれば、屁理屈っぽいですが、土壌入替費用を修繕費とすることに
納得できるような気もします。
このような解釈について、いかが思いますか。
コメントありがとうございます。
「法基通7-8-2」は資本的支出と修繕費の区別に対する通達なので、少し状況が異なるように思います。
1つ前の私の回答でもお答えしたのですが、やはり大きな理由は「取得原価を不正に小さくさせないため」という理由が大きいと考えられます。
設例として次の状況を考えてみます(土壌入替の必要性は売買時には知らなかったと想定)。
・建物付き土地(土壌入替前):5000万円
・建物撤去費用:500万円
・土壌入替費用:800万円
この土地付き建物があった場合、もし建物撤去と土壌入替を売主が行う契約であれば、販売価格(取得原価)は5,500万円になります。建物撤去費用を「建物付き土地」に上乗せするからです(土壌入替費用は想定していないので上乗せしません)。
その後、別の取引として800万円の土壌入替費用が発生します。
それに対して建物撤去と土壌入替を買主が行った場合、次のようになります。
・土壌入替費用を修繕費とした場合:取得原価5,500万円、修繕費800万円
・土壌入替費用を取得原価に含めた場合:取得原価6,300万円
売買当時に想定していない費用が後で発生した場合は取得原価に含めない方が合理的です。
逆に土壌入替の必要性を売買時に知っていた場合は、もし建物撤去と土壌入替を売主が行う契約であれば、販売価格(取得原価)は6,300万円になります。建物撤去費用と土壌入替費用を「建物付き土地」に上乗せするからです。
それに対して建物撤去と土壌入替を買主が行った場合、次のようになります。
・土壌入替費用を修繕費とした場合:取得原価5,500万円、修繕費800万円
・土壌入替費用を取得原価に含めた場合:取得原価6,300万円
売買当時に想定していた費用が後で発生した場合は取得原価に含めた方が合理的です。逆に売買当時に想定している費用を修繕費とすることで取得原価を下げることができます(仮に建物撤去費用を修繕費とすると取得原価は5,000万円まで下がります)。
建物撤去や整地などを買主が行うことで、同じ「建物付き土地」であるにもかかわらず取得原価が下がるのは適正とはいいづらいです。こういった事情が大きいと考えられます。
回答ありがとうございます。
・簿記の問題で固定資産の取得原価算定の必要が生じた際には、事実の発生した時系列と
ともに、取得原価を不正に小さく見せない、という観点は常に意識しておいた方が良い
ですね。
・この問題に限定すると、あくまでも制度会計上の問題である気がして、真の取得原価とは
何なのかが気になる僕としては、あまり好奇心がそそられませんが、現実はこうであると
割り切って理解するしかなさそうです。
質問が長くなってしまい申し訳ありませんでした。また疑問の沸いた論点が生じた際には
伺いたいと思います。ありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。真の取得原価について突き詰めていくとなかなか難しいですね。
簿記の勉強、応援しています。