- 簿記を勉強していると売買目的有価証券っていう勘定科目が出てきたんだけど……
- 売買目的有価証券の決算時の処理が分からない
- 売買目的有価証券について教えて!
同じ有価証券であっても目的が違えば会計処理方法が異なるという点が非常に難しく、簿記2級の試験でも失点してしまう方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん売買目的有価証券についても熟知しています。
この記事では簿記2級に合格するために必要な売買目的有価証券の知識について解説します。
この記事を読めば売買目的有価証券が簿記2級の試験で出題されても自信を持って解答できるようになります。
結論を言うと、売買目的有価証券は、短期的な売買益を得る目的で有価証券を取得したときに使う勘定科目です。
売却すれば現金を手に入れることができるので、売買目的有価証券は資産の勘定科目です。売買目的有価証券は決算時には時価評価をします。
売買目的有価証券とは:短期的な値上がり益の獲得が目的の有価証券

短期的な値上り益の獲得のために有価証券を購入した場合、売買目的有価証券という勘定科目を使います。
どれくらいの期間が短期なのかに厳密な決まりはなく、数日なら売買目的有価証券、数か月なら短期とは言えないのでその他有価証券、数週間ならどちらでもいいといった感じです。
売買目的有価証券とその他有価証券の違いは曖昧です。その他有価証券については「その他有価証券【仕訳と勘定科目をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
有価証券は価値のある財産なので、売買目的有価証券は資産の勘定科目となります。
売買目的有価証券は仕訳や総勘定元帳で使う「勘定科目」、有価証券は貸借対照表で使う「表示科目」という違いがあります。
また、売買目的有価証券は「短期的な値上がり益の獲得を目指して購入した有価証券」、有価証券は「1年以内に現金と交換する予定の有価証券」という違いもあります。
そのため、売買目的有価証券は全て有価証券に含まれます(短期的な値上がり目的の有価証券を1年以上売らないということはないからです)。
有価証券には売買目的有価証券以外にも「1年内に満期が到来する満期保有目的債券」も含まれます。
実際には、仕訳帳や総勘定元帳、試算表で「売買目的有価証券」として管理していたものを「有価証券」に組み替えて貸借対照表の流動資産の区分に表示します。
有価証券の購入価額=購入代金+付随費用

有価証券の購入価額は『購入代金+付随費用』です。付随費用を購入価額に含める理由は仕入諸掛を仕入勘定に含める理由でお伝えした理由と同じです。
売買目的有価証券(株式)の仕訳

株式の購入
A株式会社の株式1,000株を1株2,000円で購入し、手数料10,000円とともに小切手を振り出して支払った。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
まずは購入価額を求めなければなりません。購入価額は『購入代金+付随費用』です。購入代金は(1,000株×2,000円=)2,000,000円、付随費用は10,000円です。
購入価額は(購入代金2,000,000円+付随費用10,000円=)2,010,000円となります。小切手を振り出して支払っているので『(貸)当座預金2,010,000』です。
また、ここでは有価証券の購入の目的は特に書かれていませんが、短期的な値上り益の獲得が目的だと推測して問題ありません。
短期的な値上り益の獲得以外が目的の場合は必ず問題文に書かれます。というわけで『(借)売買目的有価証券2,010,000』です。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 2,010,000 | 当座預金 | 2,010,000 |
株式の売却
上記の株式のうち600株を1株2,500円で売却し、代金は現金で受けとった。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
まず、上記の株式の1株あたりの購入価額を求めます。1株あたりの購入価額は購入価額総額を株式数で割って求めることができます。
1株あたりの購入価額は(購入価額総額2,010,000円÷1,000株=)2,010円となります。
1株あたり2,010円で手に入れた株式を600株売却するので、減少する売買目的有価証券の価額は(1株あたりの購入価額2,010円×売却する株数600株=)1,206,000円となります。
資産の減少は貸方に記入するので『(貸)売買目的有価証券1,206,000』となります。
また、受け取る現金は「1株あたりの売却価格×売却株数」です。(1株あたりの売却価格2,500円×売却株数600株=)1,500,000円となります。
資産である現金を受け取っているので借方に記入します。『(借)現金1,500,000』となります。
このままでは借方と貸方の合計が一致しません。では、この差額(借方1,500,000円-貸方1,206,000円=)294,000円は何を意味しているのでしょうか。
この294,000円という金額は株式を売買したことによる儲けです。株式を1,206,000円で購入し1,500,000円で売却したことで発生した差額だからです。
この儲けは有価証券売却益という収益の勘定科目で表します。収益の発生は貸方に記入します。よって『(貸)有価証券売却益294,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,500,000 | 売買目的有価証券 有価証券売却益 | 1,206,000 294,000 |
売買目的有価証券(社債)の仕訳

社債の取得
A株式会社の社債額面総額2,000,000円を額面100円につき96円で売買目的で取得し、手数料20,000円とともに小切手を振り出して支払った。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
社債には額面というものがあります。額面とはその社債に書いてある金額です。額面100円とはその社債に100円と書いてあるという意味です。
額面100円の社債を96円で取得するとは額面より4円安く買えたということです。
では本題に戻ります。社債額面総額が2,000,000円で額面が100円ということは、社債を(社債額面総額2,000,000円÷100円=)20,000口買ったということです。
社債20,000口を1枚あたり96円で買ったので、(社債購入数20,000口×96円=)1,920,000円となります。
この1,920,000円が購入代金です。この1,920,000円に手数料20,000円を加えた1,940,000円が支払った金額となります。
小切手を振り出して支払っているので勘定科目は当座預金を使い『(貸)当座預金1,940,000』となります。
また、売買目的で有価証券を取得しているので『(借)売買目的有価証券1,940,000』です。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 1,940,000 | 当座預金 | 1,940,000 |
社債の売却
上記の社債を額面100円あたり95円で全て売却し、代金は後日受け取ることにした。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
まず、社債を全て売却しているので『(貸)売買目的有価証券1,940,000』です。
社債が全てなくなったので、売買目的有価証券の勘定も全てなくならなければつじつまが合わなくなります。
問題は借方です。100円あたり95円で売却しています。社債は全部で20,000口なので、(社債売却単価95円×社債売却数20,000口=)1,900,000円を受け取ることになります。
代金は後日受け取るので、勘定科目は未収金になります。
未収金は現金などを請求する権利なので資産の勘定科目です。資産が増加するので借方に記入します。『(借)未収金1,900,000』となります。
このままでは借方が40,000円少ないままです。この40,000円は損失(費用)になります。1,940,000円出して買った社債を1,900,000円で売ることになったことによる差額だからです。
売買目的有価証券を売却して出た損失は有価証券売却損という勘定科目で処理します。
費用の発生は借方に記入します。よって『(借)有価証券売却損40,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 有価証券売却損 | 1,900,000 40,000 | 売買目的有価証券 | 1,940,000 |
売買目的有価証券の複数回取得した場合の単価は移動平均法で計算する

同一銘柄の有価証券を売買目的で複数回取得した場合、有価証券の売却単価の計算方法には移動平均法を使います。
移動平均法の考え方は販売した商品の仕入単価決定方法で学習した移動平均法と同じです。商品を有価証券と置き換えれば、有価証券における移動平均法になります。
売買目的有価証券の複数回取得の仕訳

1回目の売買目的有価証券の取得
売買目的でA社の株式600株を1株あたり700円で現金で取得した。
この例題の仕訳について考えてみましょう。
株式の購入価額は(購入株数600株×1株あたり700円=)420,000円なので、次の仕訳になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 420,000 | 現金 | 420,000 |
2回目の売買目的有価証券の取得
売買目的で再びA社の株式400株を1株あたり800円で現金で取得した。
この例題の仕訳について考えてみましょう。
株式の購入価額は(購入株数400株×1株あたり800円=)320,000円なので、次の仕訳になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 320,000 | 現金 | 320,000 |
株式の売却
上記2回で取得したA社の株式800株を1株あたり1,000円で売却し、代金は現金で受け取った。
この例題の仕訳について考えてみましょう。
同一銘柄を複数回に分けて購入しているので、移動平均法で保有株式の取得単価を決定します。表でまとめると次のようになります。
| 株数 | 購入価額 | |
|---|---|---|
| 1回目 | 600株 | 420,000円 |
| 2回目 | 400株 | 320,000円 |
| 合計 | 1,000株 | 740,000円 |
この表より、保有株式の取得単価は(購入価額総額740,000円÷保有株数1,000株=)740円となります。
取得単価が740円の株式を800株売却しているので、(売却株数800株×取得単価740円=)592,000円が売却価額になります。よって『(貸)売買目的有価証券592,000』となります。
また、800株を1株あたり1,000円で売却しているので、(売却株数800株×売却単価1,000円=)800,000円の現金を受け取ったことになります。よって『(借)現金800,000』となります。
このままでは貸方が(借方800,000円-貸方592,000円=)208,000円不足しています。この208,000円は売買による利益を意味しています。
よって『(貸)有価証券売却益208,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 800,000 | 売買目的有価証券 有価証券売却益 | 592,000 208,000 |
上の仕訳の売却価額である592,000を1の仕訳も2の仕訳も切ることなく、そしてメモすることもなく求める電卓の使い方を解説します。
結論から言うと[6][00][×][7][00][M+][4][00][×][8][00][M+][RM][÷][1][00][0][×][8][00][=]で求めることができます(1,000という数字は600+400を暗算しています)。
※この電卓の使い方は「電卓のメモリー機能の使い方」で詳しく解説しています。
具体的には次の流れです。
- [6][00][×][7][00][M+]で1回目の購入価額420,000を求め、メモリーに加算
- [4][00][×][8][00][M+]で2回目の購入価額320,000を求め、メモリーに加算
- [RM]で1回目の購入価額と2回目の購入価額の合計額を表示
- [÷][1][00][0]で売却単価を求める
- [×][8][00][=]で売却価額を求める
ちなみに、このやり方を丸暗記するのはいけません。電卓の仕組みと計算の性質から、この電卓の使い方が自然と思い浮かべば理想的です。
最初からそれは難しいと思いますが、簿記2級の試験を受けるまでには身につけたい電卓の使い方です。丸暗記しても役に立たないので、丸暗記するくらいなら一つ一つ求めましょう。
売買目的有価証券は決算時に時価評価する

有価証券を保有している場合、有価証券は購入時に取得価額で記帳されています。売買目的有価証券の場合は帳簿価額を取得価額から決算時の時価に評価替えしなければなりません。
ちなみに、貸借対照表の価額を決めることを「評価」といいます。次のような勘定科目を使って仕訳を切ります。
- 時価>帳簿価額…儲けが出る…有価証券評価益(収益)
- 時価<帳簿価額…損失が出る…有価証券評価損(費用)
有価証券評価益は損益計算書の営業外収益の区分に、有価証券評価損は損益計算書の営業外費用の区分に表示します。
売買目的有価証券の時価評価の目的は企業の正しい経営成績を明らかにするためです。
正確な期間損益の算定のため、収益と費用を対応させるためともいえます。貸倒引当金を設定する目的と同じです。
売買目的有価証券の帳簿価額と時価との差額は収益であっても費用であっても、当期のものです。
仮に時価評価を行わなければ、売買目的有価証券を売却したときの会計期間に全ての損益が計上されます。それでは正しい期間損益が算定できません。
正確な期間損益の算定のためには決算での評価替えが欠かせないのです。
売買目的有価証券(1種類)の決算整理仕訳

株式の時価が下がった
決算を迎え、株式100株(帳簿価額1株8,000円)を売買目的で保有している。決算日の1株の時価は7,000円である。
この例題の決算整理仕訳について考えてみます。
まずは、株式の帳簿価額の総額と時価の総額を求めます。
- 帳簿価額:保有株数100株×1株あたり帳簿価額8,000円=800,000円
- 時価:保有株数100株×1株あたり時価7,000円=700,000円
帳簿価額を時価に修正するので、800,000円を700,000円に修正するということになります。
(帳簿価額800,000円-時価700,000円=)100,000円分帳簿価額が減少したということになります。よって「(貸)売買目的有価証券100,000」となります。
また、この100,000円は有価証券の時価が下がったことによる損失です。よって「(借)有価証券評価損100,000」となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 有価証券評価損 | 100,000 | 売買目的有価証券 | 100,000 |
株式の時価が上がった
決算を迎え、株式100株(帳簿価額1株8,000円)を保有している。決算日の1株の時価は9,000円である。
この例題の仕訳について考えてみます。
まずは、株式の帳簿価額の総額と時価の総額を求めます。
- 帳簿価額:保有株数100株×1株あたり帳簿価額8,000円=800,000円
- 時価:保有株数100株×1株あたり時価9,000円=900,000円
帳簿価額を時価に修正するので、800,000円を900,000円に修正するということになります。
(時価900,000-帳簿価額800,000=)100,000円分帳簿価額が増加したということになります。よって「(借)売買目的有価証券100,000」となります。
また、この100,000円は有価証券の時価が上がったことによる収益です。よって「(貸)有価証券評価益100,000」となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 100,000 | 有価証券評価益 | 100,000 |
基本はここまでで大丈夫です。ここから少しだけ応用的な内容についてお伝えします。売買目的有価証券が2種類以上あって、評価益と評価損が両方とも発生するような出題です。
売買目的有価証券を2種類以上保有している場合は評価益と評価損を相殺する

売買目的有価証券が2種類以上あって、評価益と評価損が両方とも発生する場合、評価損と評価益を差し引き(相殺)し、残った方(金額が多い方)だけを計上します。
原則としては、収益と費用は総額で記載しなければなりません。このことは企業会計原則に総額主義の原則として書かれています。
しかし、売買目的有価証券の売却損益、評価損益は総額主義の例外として認められています。
総額主義は取引の規模を適正に表すための原則ですが、売買目的有価証券の売買取引についてはその取引規模は重要ではないからです。
重要なのは有価証券の売買という投資活動の結果として、どれだけの損益が計上されたのかです。
大きな意味も無く売却損と売却益、評価損と評価益を区別して表示すると、その財務諸表を見た人が分かりにくくなってしまいます。
そのため、正確さよりも分かりやすさを重視するということで総額主義の例外となっています。
売買目的有価証券(2種類以上)の決算整理仕訳
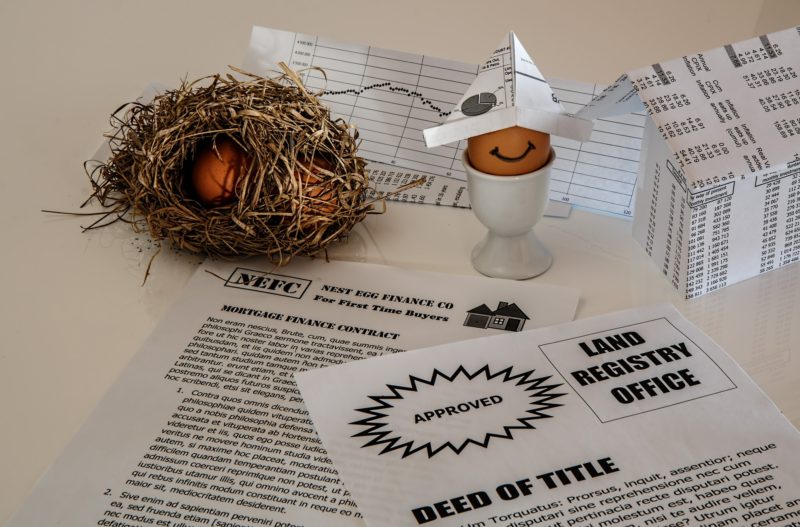
売買目的有価証券(2種類以上)の時価評価
期末に保有している有価証券は次のとおりであった。
| 銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| A社株式 | 100,000円 | 80,000円 | 売買目的 |
| B社株式 | 100,000円 | 110,000円 | 売買目的 |
| C社社債 | 100,000円 | 130,000円 | 売買目的 |
この場合の決算整理仕訳について考えてみましょう。
A社株式は「帳簿価額(100,000円)>時価(80,000円)」となっているので、評価損となります。また、金額は(帳簿価額100,000円-時価80,000円=)20,000円となります。
B社株式は「帳簿価額(100,000円)<時価(110,000円)」となっているので、評価益となります。また、金額は(時価110,000円-帳簿価額100,000円=)10,000円となります。
C社社債は「帳簿価額(100,000円)<時価(130,000円)」となっているので、評価益となります。また、金額は(時価130,000円-帳簿価額100,000円=)30,000円となります。
よって、各評価益や評価損は次のようになります。
- A社株式…評価損20,000円
- B社株式…評価益10,000円
- C社社債…評価益30,000円
「評価益(B社株式10,000円+C社社債30,000円)>評価損(A社株式20,000円)」となっているので、全体としては評価益になります。
金額は(B社株式評価益10,000円+C社社債評価益30,000円-A社株式評価損20,000円=)20,000円となります。後は仕訳を切るだけです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 20,000 | 有価証券評価益 | 20,000 |
上のように考えなくても、慣れてくればいきなり評価損益(先程の例で言えば20,000という金額)を求めることができます。
全ての売買目的有価証券の帳簿価額から全ての売買目的有価証券の時価を引くのです。
その結果、計算結果がプラスになれば「帳簿価額>時価」ということなので評価損に、計算結果がマイナスになれば「帳簿価額<時価」ということなので評価益になります。
先程の例で具体的に計算すると「100,000+100,000+100,000-(80,000+110,000+130,000)=-20,000」となります。マイナスなので評価益となります。
電卓で計算するときは[1][00][00][0][+][1][00][00][0][+][1][00][00][0][-][8][00][00][-][1][1][00][00][-][1][3][00][00][=]とすることもできます。
メモリー機能を使って、[1][00][00][0][+][1][00][00][0][+][1][00][00][0][M+][8][00][00][+][1][1][00][00][+][1][3][00][00][M-][RM]としても構いません。
ちなみに、メモリー機能を使う方法の考え方は次のような流れになります。
- [1][00][00][0][+][1][00][00][0][+][1][00][00][0][M+]と入力することで、帳簿価額の合計額をメモリーの箱に入れる
- [8][00][00][+][1][1][00][00][+][1][3][00][00][M-]と入力することで、時価の合計額をメモリーの箱から引く(この時点メモリーの箱の中は「帳簿価額の合計-時価の合計」となっています)
- [RM]と入力することでメモリーの箱の中を表示する
売買目的有価証券の時価評価の2つの会計処理
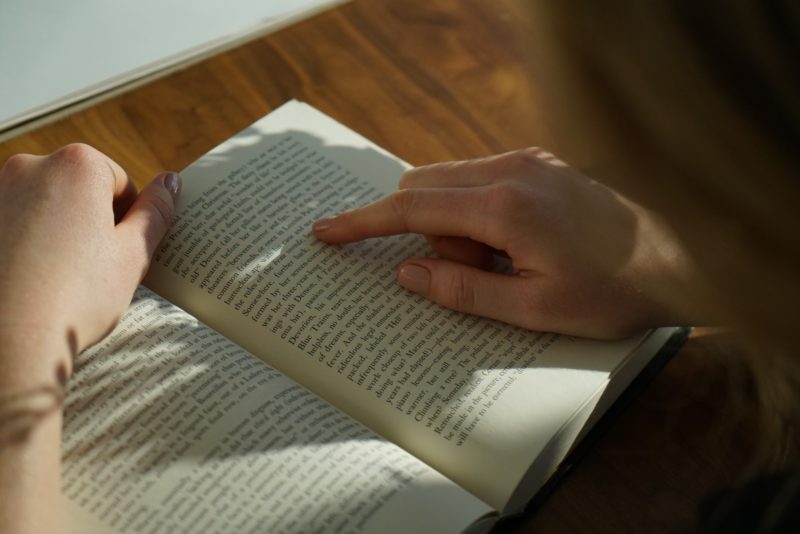
売買目的有価証券の決算整理仕訳は先ほどお伝えした通りですが、決算日の翌日(期首)の会計処理については「洗替法」と「切放法」の2つがあります。
洗替法:期首に決算整理仕訳の逆仕訳を切る方法
決算整理仕訳の逆仕訳を期首に行う方法を洗替法と言います。
洗替法の場合、貸借対照表に計上されるときだけ売買目的有価証券の評価額が決算日の時価になりますが、翌日には取得原価に戻ることになります。
切放法:期首に何もしない方法
期首には何もしない方法を切放法と言います。切放法の場合、決算整理仕訳によって決算日の時価に評価替えされた売買目的有価証券はそのままの金額で評価され続けることになります。
【まとめ】売買目的有価証券

売買目的有価証券は短期的な売買益を得る目的で有価証券を取得したときに使う勘定科目です。有価証券の購入価額は購入代金に付随費用を加算して計算します。
同一銘柄の有価証券を売買目的で複数回取得した場合、取得単価は移動平均法を使って計算します。売買目的有価証券は決算時に時価に評価替えする必要があります。
売買目的有価証券が2種類以上あり、評価益と評価損が両方とも発生する場合、評価損と評価益を差し引き(相殺)し、残った方(金額が多い方)だけを計上します。
- 弊社が運営している【簿記革命2級】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座-商業簿記2級」「暗記不要の簿記独学講座-工業簿記2級」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに簿記2級や簿記1級の合格を目指して勉強したい方は簿記2級通信講座【簿記革命2級】をご検討ください。
- 簿記2級を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記2級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法-簿記2級」で詳しく解説しています。
- 簿記2級の独学に向いたテキストについては「【2021年版】独学向け簿記2級おすすめテキスト【8つのテキストを徹底比較】」で詳しく解説しています。


コメント
■社債取得時の貸方勘定科目
小切手振出なので、
現金ではなく、当座預金ではないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおりです。小切手を振り出しているので当座預金ですね。
ご指摘ありがとうございます。至急修正します。
早々のご対応ありがとうございます。
2度も落っこちてしまって、このページに出会いました。今度こそ合格めざして頑張っています。
これからも、ご指導ください。
コメントありがとうございます。
簿記の合格目指して頑張ってください。基本を大事にして学習を続ければ次はきっと合格できると思います。簿記の学習応援しています。