- 電卓の使い方を知りたいな……
- 電卓のブラインドタッチができるようになりたいな……
- 電卓を早くミスなく打てるようになりたいな……
電卓の使い方を教わることはほとんどないので、電卓を上手に使えない、電卓を早く打てないと悩んでいる方は非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。私自身も電卓を使い続けていて、電卓についてもエキスパートです
この記事では電卓の選び方、使い方、操作方法、練習方法についてお伝えします。
この記事とリンク先の内容を全て身につけて練習を繰り返せば、あなたは電卓マスターです。
簿記検定におすすめの電卓

簿記検定では次の3つの電卓がおすすめです(PR)。
どれかを選べば間違いありません。私としては「SHARP 学校用電卓 EL-G37」がおすすめです。
私は「SHARP 学校用電卓 EL-G37」の旧型である「SHARP 学校用電卓 EL-G35」を20年以上愛用しています。値段はお高めですが、最高品質です。
≫具体的な選び方など、詳しくは「【日商簿記検定3級・2級・1級共通】電卓おすすめ3選【初心者にもおすすめ】」で解説しています。
各種キーの機能説明

使う電卓を決めたら次は電卓の操作方法を身につけましょう。電卓にはたくさんのキーがありますが、それらのキーの使い方について説明していきます。
小数点の使い方
小数点の使い方にそれほど特別なものはありませんが、小数点の前の0は省略することができます。
0を最初に入力しても構わないのですが、できるだけ入力数を減らすことが早く打てることにもミスを減らすことにもつながります。
≫詳しくは「電卓のおかしい小数点を消す設定方法【Fに合わせて】」で解説しています。
電卓のCとCEとCAの違いと桁下げキーの使い方
CとCEとCAは全て情報を消去するキーですが、役割が異なります。それぞれの役割は次のとおりです。
- クリアキー(C):メモリー情報以外を消去する
- クリアエントリーキー(CE):いま表示されている画面の数字を消去する
- オールクリアキー(AC,CA):電卓の全ての情報を消去する
≫詳しくは「電卓のCE・C・CA(AC)・CM(MC)の意味の違い」で解説しています。
電卓のプラスマイナス(+/-)の使い方
多くの電卓にはプラスマイナスキー(+/-)がついています。このプラスマイナスキーはプラスとマイナスを入れ替えるためだけのものではありません。
引き算は通常(引かれる数)[-](引く数)[=]で計算しますが、サインチェンジキーを使うことで、(引く数)[-](引かれる数)[=][+/-]で計算することもできるのです。
この使い方をすることで、例えば「30-15÷5×2」などを途中でメモすることなく電卓のみで計算することができます。
≫詳しくは「電卓のプラスマイナス【+/-】【±】の本当の使い方」で解説しています。
電卓のGT(グランドトータルキー)の使い方
GT(グランドトータルキー)は小計をいくつか求めたあとに、最終的に小計の合計を求めたい場合に使います。
[GT]を押すことで、[=]の後に表示される数字の合計が表示されます。
≫詳しくは「電卓のGT(グランドトータルキー)の意味とは」で解説しています。
電卓のパーセントキー(%)の使い方
電卓のパーセントキーには次の5つの使い方があります。
- ○%を求めるときには、[×][○][%]と入力します。
- ○%増しを求めるときには、[×][○][%][+][=]と入力します。
- ○%引きを求めるときには、[×][○][%][-][=]と入力します。
- ○は□の何%かを求めるときには、[○][÷]□][%]と入力します。
- ○は□の何%増しかを求めるときには、[○][÷]□][%][-][1][00][=]と入力します。
≫詳しくは「パーセント計算の電卓の5つの使い方【割合計算・割増計算など】」で解説しています。
電卓のルートキー(√)の使い方
ルート(√)はざっくりと言うと「2乗したらその数になる数のうちプラスの方」で、例えば√16であれば4になります(4×4=16だからです)。
数字のあとにルートキー(√)を押すとルートされた数が表示されます。
≫詳しくは「【簿記1級で使用】電卓のルートキー(√)の使い方」で解説しています。
電卓のメモリー機能の使い方
電卓には非常に便利なメモリー機能が搭載されています。メモリー機能に関するキーは次の4つです。
- メモリープラスキー(M+)…表示されている数値をメモリーに足す
- メモリーマイナスキー(M-)…表示されている数値をメモリーから引く
- リターンメモリーキー(MR,RM)…メモリーの数値を表示する
- クリアメモリーキー(MC,CM)…メモリーの数値を消す
メモリー機能を使うことで複雑な計算も途中でメモすることなく計算することができます。
≫詳しくは「【簡単】電卓のメモリー機能の使い方【シャープとカシオは同じ】」で解説しています。
電卓での定数計算の方法
定数計算はキーで行うものではなく、電卓に備わっている機能です。定数計算キーというものがあるわけではありません。
定数計算には次の4種類があります。
- 定数加算:同じ数字にさまざまな数字を加算する計算
- 定数減算:さまざまな数字から同じ数字を引く計算、同じ数字を何度も引く計算
- 定数乗算:同じ数字にさまざまな数字をかける計算、同じ数を何度もかける計算
- 定数除算:さまざまな数字を同じ数字で割る計算、同じ数字で複数回割る計算
定数計算は通常の電卓の使い方であれば何度も同じ数字を入力する必要があります。ですが電卓に備わっている機能をうまく使うことで同じ数字の入力を減らすことができるのです。
≫詳しくは「定数計算【シャープ電卓とカシオ電卓どちらも解説】」で解説しています。
電卓の日数計算の使い方
電卓の中には日数の計算ができる機能がついたものがあります。「日数(月・日)」のようなボタンがあれば、日数計算ができる電卓です。
日数計算の機能を使うと、例えば「1月26日」から「10月20日」まで何日あるのか計算することができます。
ちなみに、先程の例の操作方法は「日数(月・日)」[1][日数][26][~][10][日数][20][=]です。
≫詳しくは「【簿記】電卓の日数計算のやり方【おすすめ電卓も紹介】」で解説しています。
電卓の時間計算の使い方
電卓の中には時間の計算ができる機能がついたものがあります。「時間(時・分・秒)」のようなボタンがあれば、時間計算ができる電卓です。
時間計算の機能を使うと、例えば「8時25分36秒」から「14時36分12秒」まで何時間何分何秒あるのか計算することができます。
ちなみに、先程の例の操作方法は「時間(時・分・秒)」[1][4][時間][3][6][時間][1][2][時間][-][8][時間][2][5][時間][3][6][時間][=]です。
≫詳しくは「電卓の時間計算の使い方【おすすめ電卓も紹介】」で解説しています。
電卓での分数計算のやり方
減価償却の月割など、簿記では分数をかけることがよくあります。その場合、「÷分母×分子」と計算すると「99999…」というような永遠に続く小数になることがあります。
永遠に続く小数を避けるためには「×分子÷分母」というように掛け算を先に行う必要があります。しかし、計算の意味を考えると「÷分母×分子」の方が適切な場合が多いです。
「×分子÷分母」とするよりも「99999…」に慣れることをお勧めします。
≫詳しくは「電卓(計算機)での分数計算のやり方【分数計算機のおすすめも】」で解説しています。
電卓練習

電卓の使い方を身につけたら、次は電卓を素早く操作できることを目指しましょう。
簿記検定にピッタリの電卓の使い方:左手5本指がおすすめ
電卓の操作は使う手「左手or右手」と使う指「3本指or4本指or5本指」の6パターンがあります。この中で私がお勧めなのは「左手5本指」です。
簿記検定で電卓を使う人は左手5本指で電卓操作を行うことをお勧めします。
≫詳しくは「簿記検定にピッタリの電卓の使い方(左手5本指がおすすめ)」で解説しています。
また、左手5本指以外の操作方法については「【電卓版】ブラインドタッチの練習の前に【指使いを決める】」で詳しく解説しています。
電卓の早打ちに必要なことは操作方法の理解とブラインドタッチの習熟
電卓の早打ちに必要なことは「基本的な操作方法を身につけること」と「電卓のブラインドタッチを身につけること」です。
基本的な操作方法を身につけることで無駄なキー操作を減らし、意味のあるキー操作だけを行うようにします。その上で、その意味のあるキー操作をブラインドタッチで正確に早く行うのです。
≫詳しくは「電卓の早打ちに必要なたった2つのこと」で解説しています。
電卓練習用計算問題
ブラインドタッチの練習には電卓の計算問題を繰り返し練習する必要があります。練習するときには次の意識が大切です。
- 同じボタンは必ず同じ指で入力する
- 手許は絶対に見ない
- リズミカルに指を動かす
この3つを意識しながら次の「電卓練習用計算問題(電卓版ハノン)【無料プリントあり】」で繰り返し練習してください。
簿記における電卓での注意点
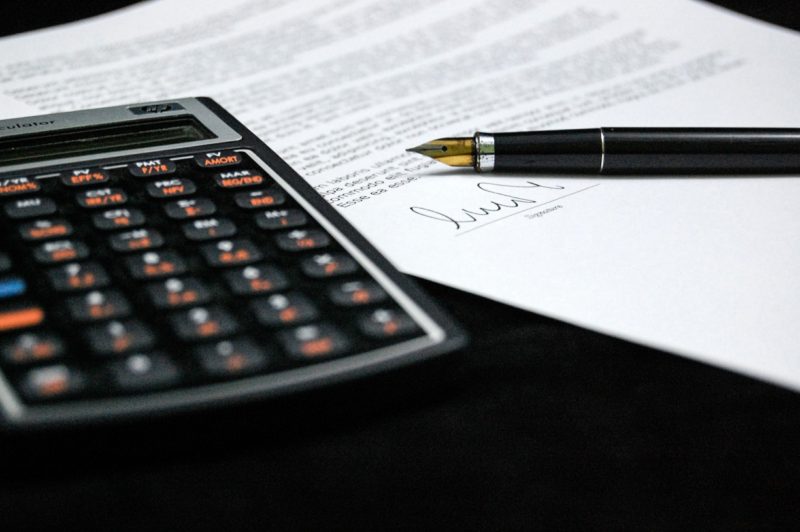
簿記試験に電卓を忘れてしまったときの対処法
もし試験本番に電卓を忘れてしまったら相当あせります。もし忘れてしまっても、きちんと実力があれば簿記3級であれば十分合格可能です。
簿記2級でも相当の実力があれば何とか合格できます。簿記1級の合格はほぼ不可能です。
≫詳しくは「【簿記3級に電卓はいらない?】簿記試験に電卓を忘れたら合格できるのか」でお伝えしています。
【簿記】電卓で計算ミスする原因とその対策
簿記での計算ミスは次の3つのいずれかに原因があります。
- 簿記の理解不足
- 問題の読み間違い、数値の読み間違い
- 電卓の操作ミス
計算ミスをしたら3つの中のどのミスをしてしまったのかをチェックしてみてください。そして、多いミスを減らすよう意識すれば効率よくミスを減らすことができます。
また、総合問題で貸借が一致しなかった場合は次の方法でミスしたところを特定することができます。
- 不一致額がきりのいい数字の場合:数字を見間違えている可能性が高い
- 不一致額そのものの金額が仕訳にある場合:借方か貸方のどちらかに記入を忘れている可能性が高い
- 不一致額を2で割った金額が仕訳にある場合:借方か貸方のどちらかに2つとも記入している可能性が高い
- 不一致額を9で割った金額が仕訳にある場合:借方か貸方のどちらかの金額の読み間違いかケタ違いの可能性が高い
このどれにも当てはまらなかった場合は2ヶ所以上まちがえてしまっています。その場合は簡単にはミスの場所を特定できないので一つ一つ確認する必要があります。
≫詳しくは「【簿記】電卓で計算ミスする3つの原因とミスを減らす方法」で解説しています。
【まとめ】ここまでたどりついたあなたは電卓マスターです

これまで電卓の選び方、操作方法、練習方法をお伝えしてきました。これまでの記事とリンク先の内容を身につければ電卓マスターです。
電卓マスターも練習を怠れば衰えてしまいますので、電卓練習の継続は大切です。
≫電卓練習用計算問題(電卓版ハノン)【無料プリントあり】
- 弊社が運営している【簿記革命】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに日商簿記の合格を目指して勉強したい方は【簿記革命】をご検討ください。
- 簿記を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法」で詳しく解説しています。

