- 工業簿記を勉強していると製造間接費の予定配賦っていう内容が出てきたんだけど……
- 製造間接費の予定配賦を行う理由が分からない
- 予定配賦率と予定配賦額の求め方を教えて!
製造間接費は予定配賦が原則ですが、なぜ予定配賦を行うのか分からない方が多いです。結果、予定配賦率や予定配賦額の計算も難しいと感じてしまうことになります。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん予定配賦を行う理由も予定配賦率や予定配賦額の計算も熟知しています。
この記事では製造間接費の予定配賦を行う理由や予定配賦率・予定配賦額の求め方について解説します。
この記事を読めば、製造間接費の予定配賦が理解できるので、簿記2級で製造間接費の予定配賦の問題が出題されても自信を持って解答できるようになります。
結論を一言で言うと、製造間接費の予定配賦は計算を速く行うため、配賦率を一定にするために行います。予定配賦率は「製造間接費予算額」を「予定配賦基準数値の合計」で割ることで求めます。
製造間接費を予定配賦する2つのメリット

製造間接費の実際配賦には「計算が遅い」「実際配賦率が管理できない状況に影響される」という2つの問題点があります。
製造間接費については「製造間接費とは【配賦額の求め方をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
製造間接費の実際配賦の問題点については「製造間接費の実際配賦【実際配賦の問題点も解説】-製造間接費の実際配賦の問題点【解決したのが予定配賦】」で詳しく解説しています。
「計算が遅い」「実際配賦率が管理できない状況に影響される」という2つの問題点を解決するために予定配賦があります。当然、予定配賦のメリットは次の2点になります。
- 計算が速い
- 配賦率が一定になる
計算が速い
予定配賦では前もって予定配賦率というものを決めておきます。
前もって決めておくので、製品が完成し、製品についての配賦基準数値が集計できた時点でその製品について製造間接費の配賦額が計算されます。
実際配賦では翌月にしか計算できなかったものが製品完成後すぐに計算できるようになるため、計算が速くなっています。
配賦率が一定になる
実際配賦の配賦率が生産量によって変動する理由は「製造間接費の中に固定費があるから」です。
固定費というのは生産量に関わらずに同額が発生する費用です。家賃や保険料のようなものです。固定費があるために、生産量が減ることで配賦率が上がります。
固定費というものは、生産設備を維持するためにかかるものです。使うことでかかるものではありません。
そこで、固定費は実際の生産量で配賦するよりも、1ヶ月あたりの生産量の平均で配賦したほうが合理的です。
1ヶ月あたりの生産量の平均を基準操業度といいます(1年間の場合もあります)。基準操業度については「基準操業度とは【4種類の求め方をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
1ヶ月あたりの生産量の平均で配賦することで配賦率が一定になります。
「計算が速い」「配賦率が一定になる」というメリットがある予定配賦を採用することで原価管理に役立ちます。
計算が速いため対策も早く打てますし、製造間接費の実際発生額と予定配賦額を比べることで適切な原価管理もできます。
これからは予定配賦の学習を中心に行っていくことになります。
固定費があることで製造原価が変わる理由の説明

固定費があることで製造原価が変わる理由をやや極端な具体例を使って解説します。
固定費が大きい場合は生産量が変わると製品1個あたりの製造原価も変わる
次の例を考えてみましょう。
- 変動費:1個あたり100円
- 固定費:1月あたり5,000,000円
変動費に対して固定費が極端に大きいと感じるかもしれませんが、複製が低コストでできる音楽CDやゲームソフトなどではこのような割合になることも珍しくありません。
では、この例で「100個生産した場合」と「10,000個生産した場合」について考えてみましょう。
(例)100個生産した場合の製品1個あたりの製造原価は50,100円
100個生産するので、変動費は(1個あたり変動費100円×生産量100個=)10,000円となります。また、固定費は生産量に関わらず5,000,000円です。
よって、この月における製造原価は(変動費10,000円+固定費5,000,000円=)5,010,000円となります。1個あたりの製造原価は(製造原価5,010,000円÷生産量100個=)50,100円となります。
(例)10,000個生産した場合の製品1個あたりの製造原価は600円
10,000個生産するので、変動費は(1個あたり変動費100円×生産量10,000個=)1,000,000円となります。また、固定費は生産量に関わらず5,000,000円です。
よって、この月における製造原価は(変動費1,000,000円+固定費5,000,000円)=6,000,000円となります。1個あたりの製造原価は(製造原価6,000,000円÷生産量10,000個=)600円となります。
固定費がない場合は生産量が変わっても製品1個あたりの製造原価は変わらない
次の例を考えてみましょう。
- 変動費:1個あたり100円
- 固定費:0円
固定費が0円というのは少々考えにくいですが、生産量に応じて家賃が決まるといったような特殊な契約で生産している場合には起こりえます。
では、この例で「100個生産した場合」と「10,000個生産した場合」について考えてみましょう。
(例)100個生産した場合の製品1個あたりの製造原価は100円
100個生産するので、変動費は(1個あたり変動費100円×生産量100個=)10,000円となります。固定費はありません。よって、この月における製造原価は10,000円となります。
1個あたりの製造原価は(製造原価10,000円÷生産量100個=)100円となります。
(例)10,000個生産した場合の製品1個あたりの製造原価は100円
10,000個生産するので、変動費は(1個あたり変動費100円×生産量10,000個)=1,000,000円となります。固定費はありません。よって、この月における製造原価は1,000,000円となります。
1個あたりの製造原価は(製造原価1,000,000円÷生産量10,000個=)100円となります。
固定費がなければ変動費が1個あたりの製造原価になります。
このように、固定費が大きければ大きいほど生産量の変化に対して1個あたりの製造原価が大きく変動することになります。
製造間接費の予定配賦の計算手順:予定配賦率→予定配賦額→差異分析
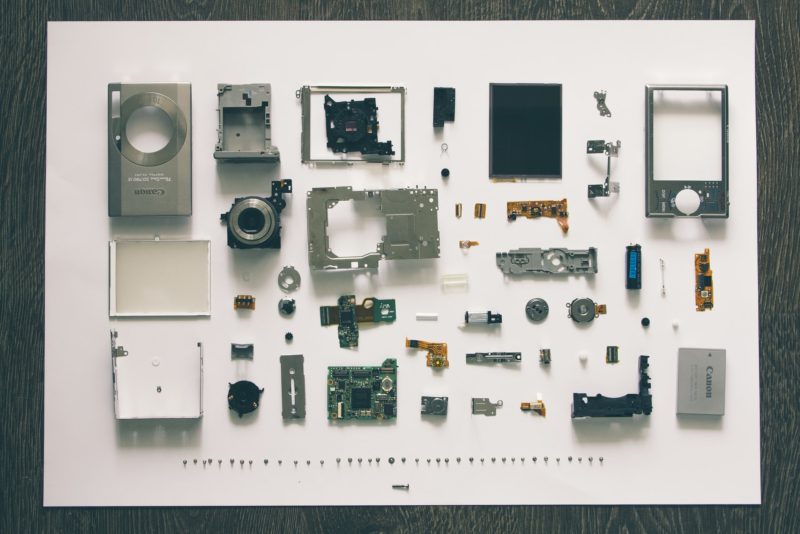
製造間接費の予定配賦は次のような計算手順で行います。
- 予定配賦率の計算
- 予定配賦額の計算
- 実際配賦額と予定配賦額の差額の把握と分析
1.予定配賦率の計算:一定期間の製造間接費予算額÷同期間の予定配賦基準数値合計
次の計算式で予定配賦率を求めます。
予定配賦率=(一定期間の製造間接費予算額)÷(同期間の予定配賦基準数値合計)
また、予定配賦基準数値合計のことを基準操業度といいます。この計算式の意味を理解するために具体例で考えてみましょう。
- 1年間の製造間接費予算額:5,000,000円
- 予定配賦基準:直接作業時間
- 1年間の直接作業時間:2,500時間
このような状況があった場合、予定配賦率は(1年間の製造間接費予算額5,000,000円÷1年間の直接作業時間2,500時間=)2,000円/時となります。
「2,000円/時」という数値は直接作業時間1時間あたり2,000円の製造間接費が発生すると見積もっているということを意味しています。
2.予定配賦額の計算:予定配賦率×製品ごとの実際配賦基準数値
次の計算式で予定配賦額を求めます。
予定配賦額=予定配賦率×製品ごとの実際配賦基準数値
この計算式の意味を理解するために上の例の続きを考えてみましょう。
- 予定配賦率:2,000円/時
- A製品の直接作業時間:80時間
- B製品の直接作業時間:120時間
このような状況があった場合、A製品の予定配賦額は(予定配賦率2,000円/時×A製品の直接作業時間80時間=)160,000円となります。
また、B製品の予定配賦額は(予定配賦率2,000円/時×B製品の直接作業時間120時間=)240,000円となります。
予定配賦額は予定配賦率にもとづいて配賦した製造間接費です。
3.実際配賦額と予定配賦額の差額の把握と分析
予定配賦額というのはあくまでも予定の配賦率を見積もって求めた金額です。よって、通常は実際にかかった費用との差額が発生します。
予定配賦額と実際配賦額の差額がどのような性質のものなのかを分析することで原価管理を行います。
製造間接費を予定配賦したことによる差異の分析については「製造間接費配賦差異の求め方【シュラッター図と計算式で解説】」で詳しく解説しています。
また、製造間接費の予定配賦の仕訳については「製造間接費の予定配賦の仕訳」で詳しく解説しています。
【まとめ】予定配賦率の求め方と予定配賦額の求め方

製造間接費の予定配賦は計算を早く行うため、配賦率を一定にするために行います。
製造間接費の予定配賦は次のような計算手順で行います。
- 予定配賦率の計算:予定配賦率=(一定期間の製造間接費予算額)÷(同期間の予定配賦基準数値合計)
- 予定配賦額の計算:予定配賦額=予定配賦率×製品ごとの実際配賦基準数値
- 実際配賦額と予定配賦額の差額の把握と分析

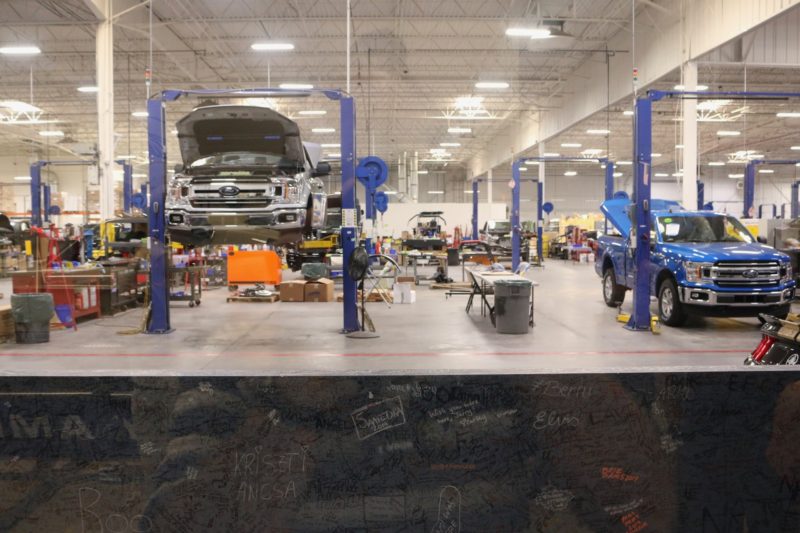
コメント
製造間接費「予定」配賦額を計算する際に、当月「実際」直接作業時間を使うのだろうというのが疑問でなりませんでしたが、これ読んで、すっきりしました。予定配賦の成り立ちを理解すると腹落ちしますね。
コメントありがとうございます。お役に立てて何よりです。