- 簿記のテキストって何回くらい読んだらいいんだろう……。
- 簿記のテキストにどんな書き込みをしたらいいのか分からない
- 簿記のテキストの効果的な読み方を教えて!
簿記の実力を効果的につけていくためにはテキストを効果的に使っていくことが大切ですが、どういうことを意識して何回くらい読めばいいのかなど、簿記のテキストの使い方に悩んでいる人が多いです。
私は日商簿記に合格するための通信講座を2012年から運営し、これまでに数百人の合格者を送り出させていただいています。もちろん簿記のテキストの効果的な使い方も熟知しています。
この記事では、勉強の進み具合に応じたテキストの読み方を具体的にお伝えします。
この記事を読めば、効率よくテキストを使っていくことができるので、インプットの時間を効果的に使い、その分アウトプットに時間を使えるようになります。
結論を一言で言うと、最初に読むときは難しく考えすぎず、さらりと読むだけで構いません。そのあと問題を解いて間違えてしまったら、そのときは理解不足のところを注意深く読みます。その後は気になったときに書き込み部分や下線部分を中心に読み返すだけで十分です。
勉強の進み具合に応じた簿記のテキストの効果的な読み方
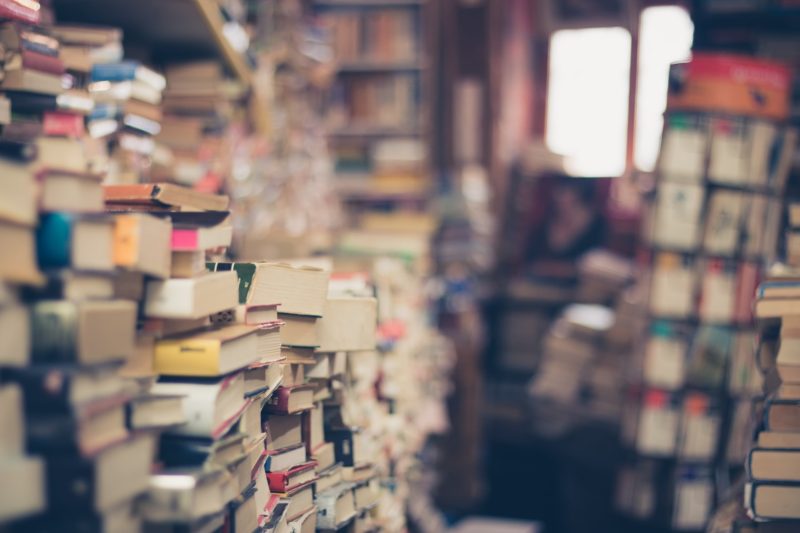
テキストを効果的に読むタイミングは次の3つです。
- その内容を始めて勉強するとき:難しく考えすぎず、さらりと読む
- 問題を解いた後:間違えてしまった場合は理解不足だと感じるところを注意深く読む
- 問題を解けるようになった後:書き込み部分や下線部分を中心にざっと確認する
その内容を始めて勉強するときはテキストをさらりと一読する
簿記という学問は「テキストを読む」ということにそれほど時間を使う必要はありません。
新しい内容を学習するときに読んだだけで全てを理解するのは非常に難しいことなので、最初のテキスト読みの段階で全てを理解しようとすると精神的にストレスがかかってしまい、勉強を続けることが苦痛になってきます。
そこで、最初は難しく考えず、さらりと読むという意識で十分です。そして、その部分に対応した問題を解いてみます。
中学校で学習する科目の中で簿記という学問に最も近い科目は「数学」です。数学は学問の中でも「スポーツ」に近い性質があり、具体的には「理解していることと問題が解けることに大きな違いがある」という性質があります。
こういった性質があるものを身につけようとする場合、「色々な知識や考え方をインプットしているけれど練習等のアウトプットが足りていないという状態」になってしまうと効率よく実力をつけていくことは難しくなります。
これを避けるには、「知ったこと、理解したことは必ず問題練習をしてできるようにする」という意識が必要です。こういった意識でテキストを読むと「難しく考えず、さらりと読む」という形になるのです。
テキストを読むときは「知ったこと、理解したことは必ずできるようにする」という意識で読むことが大切です。
問題集を解いた後は間違えてしまった理由をなくす意識で読む
問題を解いたとき、その問題がさらりと解けるようであれば、とりあえず理解すべきことは理解していると考えて大丈夫です。テキストをもう一度読み直す必要も特にありません。
しかし、問題を間違えてしまった場合は、何か理解すべきことを理解できていないところがあるということです。その「理解すべきこと」を探す意識でもう一度テキストを読むことが大切です。
そして、「理解していなければならなかったところ」に下線を引いたり、余白に書き込んだりしておきます。
理解し直してもう一度同じ問題を解き、今度は正解できればそれで十分です。
問題が解けるようになった後は特に読まなくてもよい
問題が解けるようになったのであれば、基本的にテキストを読む必要はありません。ですが、問題を解く力がついたあとでもう一度読むと、一度目には気づかなかった点に気づいたり、さらに理解が深まったりすることもよくあります。
なので、もう一度読んでみることに十分価値もあります。そうやってもう一度読むときは、細切れ時間で拾い読みがおすすめです。ちょっとした時間にさらりと、下線部分や書き込み部分を中心に読むといいです。
【まとめ】簿記のテキストの効果的な読み方使い方

新しい内容に入るときに、まず最初にテキストを読みます。最初に読むときはあまり難しく考えず、さらりと読み、問題を解いてみます。問題が解ければとりあえず大丈夫です。
もし間違えてしまったら、理解不足の部分を探して理解し直すつもりで読みます。重要だと感じた部分には下線を引いたり書き込みをしたりしておきます。そして、理解できたと思ったらもう一度同じ問題を解き、そこで正解できれば大丈夫です。
その後、細切れ時間などで下線部分や書き込み部分を中心に軽く読み返します。このときに、最初に読んだときには気づかなかったことに気づくこともよくあります。
このような形でテキストを使っていけば、効果的にインプットを行うことができるようになります。

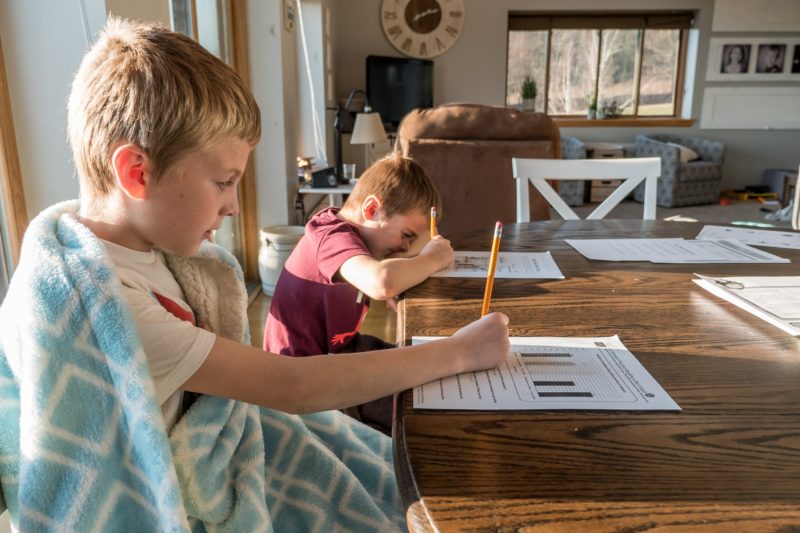
コメント