- 日商簿記1級は相対評価の試験だって聞いたことがあるんだけど……
- 日商簿記1級が本当に相対評価なのか分からない
- 日商簿記1級が相対評価なら、どんな勉強をしたらいいのか教えて!
日商簿記検定は「70%以上の得点で合格」と商工会議所が公表していることもあり、70点以上得点できれば合格できると思っている方が多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん日商簿記1級の採点方式についても、どのような勉強をしたらいいのかについても熟知しています。
この記事では日商簿記1級が相対評価の試験であるということ、相対評価の試験であるならばどのような勉強をすべきなのかについて解説します。
この記事を読めば、日商簿記1級という試験の本質、日商簿記1級に合格するためにはどのようなスタンスで勉強したらいいのかが分かります。
結論を言うと、日商簿記1級は70点得点できた人が合格できる絶対評価の試験ではなく、上位10%の人が合格できる相対評価の試験です。
日商簿記1級に合格するためには「他の受験生の正解率が高い問題」を正解できるようになることが大切です。
絶対評価と相対評価の違い

日商簿記検定に限らず、全ての試験は「絶対評価」と「相対評価」のどちらかで合否を判断しています。
絶対評価:ある基準に到達しているかどうかで合否を判定する方法
絶対評価とは「ある基準に到達しているかどうかで合否を判定する方法」です。
合格基準が「〇点得点できれば合格」「〇%得点できれば合格」といったものであれば、その試験は絶対評価であると言えます。
問題の難易度が同じであることが前提ですが、絶対評価の試験は回が違っても合格者のレベルが同じになるという長所があります。
極端な例ですが、もし全員が合格点に達した場合は全員が合格して合格率100%、全員が合格点に達しなければ全員が不合格で合格率0%になるのが絶対評価の試験です。
相対評価:集団の中でどれだけ上位に位置しているのかで合否を判定する方法
相対評価とは「集団の中でどれだけ上位に位置しているのかで合否を判定する方法」です。
合格基準が「上位〇%」「上位〇人」いったものであれば、その試験は相対評価であると言えます。
相対評価の試験の場合、受験者全体のレベルが低い回は実力不足でも合格できるのに対し、受験者全体のレベルが高い回は合格する実力があっても合格できません。
こういった理由から、相対評価の試験は「受験者の能力を保証する」という目的の試験では採用されません。
しかし、合格率や合格者数が安定するので、現実的に合格者数に制限をつけなければならない場合には相対評価が使われます。
具体的には「政策上、需要と供給をバランスさせなければならない国家資格」や「教室などの収容人数に制限がある高校や大学」などでは相対評価が使われます。
簿記2級までは絶対評価、簿記1級は相対評価

日商簿記検定は級を問わず、「70%以上得点できれば合格」となっています。
つまり、表向きは絶対評価の試験であるように見えます。しかし、実際には簿記1級だけは相対評価であると考えられます。
簿記1級だけは簿記2級までと違って合格率が安定しすぎているからです。
表向きは絶対評価であるとしながら、実際には相対評価にするために「傾斜配点」という採点方法が使われます。
傾斜配点を行うことで正答率が高い問題に大きな配点をが与えられます。そうすることで、70%以上得点できた人の人数が受験者数の10%になるように調整するのです。
簿記1級は相対評価の試験であるということを踏まえて勉強することが大切です。
日商簿記検定は税理士試験や司法試験などと違い、合格しても何か独占業務ができるわけではありません。言い換えれば、日商簿記検定は合格者数が変化しても社会に与える影響は少ないのです。
ではなぜ日商は表向きではなく、本当に絶対評価にしないのでしょうか。
それは「日商簿記1級が日商簿記の中で最高峰の試験だから」です。最高峰の試験なので合格者が増えすぎてしまうと合格の価値が下がってしまいます。
合格の価値を下げないために「合格者は1,000人前後にしよう」「合格率は10%前後にしよう」というように合格者が増えすぎないよう調整しているのです。
それなら最初から相対評価にして「合格者は1,000人前後」「合格率は10%前後」と公開していればいいと思うかもしれません。
しかし、相対試験は試験の合否が受験者のレベルに左右されます。相対試験にするということは、回によって合格者のレベルが違うことを日商自体が認めてしまうことになります。
回によって合格者のレベルが違ってしまうと、「合格者の能力を保証する」のが目的である資格試験(検定試験)としては問題があります。
こういった事情から、「70点以上は合格」と表向きには絶対評価にしながらも、実際には非公式で合格者数を調整する相対試験にしているのです。
簿記1級が相対評価であるという前提で行うべき勉強のスタンス

簿記1級は実質的には相対評価の試験です。正答率が高い問題に大きな配点が与えられるので、正答率が高い問題を確実に正解する意識で勉強する必要があります。
ここで意識しなければならないのは「他の受験生」がどんな人なのかです。
簿記1級は様々な人が受験しますが、多い方から順番に次の3タイプが存在します。
- 純粋に簿記1級の合格を目指す人
- 受験資格を得るために簿記1級を受験する税理士受験生
- 腕試しに簿記1級を受験する会計士受験生
この3タイプの正答率が高い問題を確実に得点できるように勉強することが簿記1級の合格の近道です。
まずは全員の正答率が高い「簿記3級と簿記2級の全て」と「簿記1級の基本問題」を確実に得点することが大切です。そのうえで、各タイプが得意な論点・問題を得点できれば合格できます。
【まとめ】日商簿記1級は相対評価である前提で勉強しよう

日商簿記1級は表向きは「70%以上得点」で合格できる絶対評価の試験ですが、本当は「上位10%」が合格できる相対評価の試験です。
表向き絶対評価の試験を相対評価にするために「傾斜配点」という採点方式が採用されています。
傾斜配点が行われることで、正答率が高い問題に大きな配点が与えられます。そのため、正答率が高い問題を確実の得点することを目指して勉強することが大切です。
簿記1級は様々な人が受験しますが、多い方から順番に次の3タイプが存在します。
- 純粋に簿記1級の合格を目指す人
- 受験資格を得るために簿記1級を受験する税理士受験生
- 腕試しに簿記1級を受験する会計士受験生
この3タイプの正答率が高い問題を確実に得点できるように勉強することが簿記1級の合格の近道です。
まずは全員の正答率が高い「簿記3級と簿記2級の全て」と「簿記1級の基本問題」を確実に得点することが大切です。そのうえで、各タイプが得意な論点・問題を得点できれば合格できます。
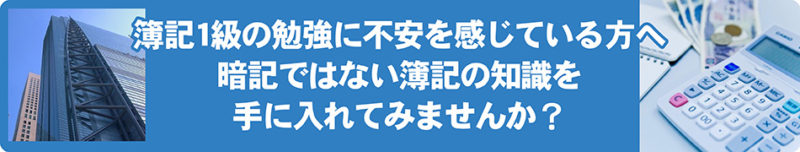

コメント
こんにちは。
初めて立ち寄りました。
日商簿記1級取得者が周りに少ない理由の私の考えを言います。
それは。1度合格している人が、何回も受験しているからです。
何年か前、笑っていいともに日商簿記1級を100点取った人が出ていました。
たぶん、遊び感覚で、すでに1級を持っている人が、何回も1000点狙って、受けてるのだろうと推測できます。私も現在勉強中ですが、過去問のなったとたん、全く分からなくなりました。ちなみの独学です。理系の私には難しすぎます。もう一つは、資格学校の講師が1級を受けて、資格学校の合格者数を跳ね上げていると推測します。間違いありません。それが、日商1級取得者が身近にいない理由だと思います。
純粋に初めて合格する人は100人いないかもしれません。
たぶん、間違えないと思います。
コメントありがとうございます。
確かに何度も受けている方いらっしゃいますね。受験料がそこそこ高いので、それほど多くないとは思っていますが、それでもそれなりにいらっしゃいます。おっしゃるとおりだと思います。
資格学校の講師は確かに簿記検定を受けるのですが、それは合格者数を跳ね上げるためというよりも、最速で解答速報を出すのが目的です。退席許可が出た瞬間に退席する人の中にそういった人たちが紛れています(その後、講師陣が集まって解答し、試験時間の終了までに模範解答を作成し、試験会場を出る人にその場で配布します)。彼らは合格が目的ではないので、合格しているかは微妙ですね。
合格率とは関係ありませんが、簿記1級で満点合格された方は笑ってコラえてという番組の検定試験の旅という企画で2009年頃に見た記憶があります。
満点合格された女性の方は2級合格率が5.7%の107回に71点で合格され、寝る間も惜しみ116回の1級で満点合格されたそうです。その時に番組内で15万人受験して満点合格は3人しかいないと仰っていました。簿記検定1級の奥深さが伺えますね。
また1級で過去最低の合格率の84回の試験では原価計算が設備投資の意思決定で運転資本を考慮しなければいけなくかなりの難問で白紙回答でも5点になったという書き込みを見たこともあります。
2級だけではなく1級も年々難しくなっていると感じていますが、長い簿記検定の歴史を振り返ると近年以上に難しい回もあるように感じます。
合格率とは関係ない内容ですみません。
コメントと貴重な情報ありがとうございます。合格率と関係ない内容でも全く問題ありません。
簿記1級は満点を取るのが非常に難しく、簿記2級までと違って、満点を狙って勉強すると手を広げすぎてしまい逆効果になってしまうこともあります。それにしても15万人が受けて3人しかいないというのはすごいですね。
84回の「白紙回答でも5点になった」というのは興味深いです。簿記に限らずどのような試験でも「模範解答なら満点」「白紙回答なら0点」というのが原則ですが、その原則をくつがえす傾斜配点というのは相当です。
確かに過去には非常に難しい回というものはありました。その回だけ見れば、やりすぎだと思うほどですね。ただ、過去は難易度を間違って難しくしてしまったという印象で、その次の回はリバウンドで合格率が上がっています。それと比較すると、近年は合格率の低い回が続いていて、日商の意志を感じます。「これからはこれでいくぜ」といった感じでしょうか。
3級~1級全てに共通して言える事だと思いますが、出題者にとっては簡単な問題で解答者にとっても簡単な問題であっても「なぜか解けない問題」というのが多いから
3、2級では回によって大きく合格率が大きく変動し1級でも極端に合格率が高くなる
という事も無いんだと思います。
薬剤師等の一部の国家試験のように難関なのに合格率がやけに高い試験みたいに
真面目にきちんと勉強してきた人が受験するのなら合格率がもっと高くなるはずです。
要するに受験する側の勉強不足が原因で1級では特に傾斜配点無しでは合格率が一桁前半何てこともざらにあるんだと思います。
3,2級でも問題が難しいから合格率が変動するのではなく単なる受験する側の
勉強不足が一番の問題ですよ。
こういう事は資格スクール側は絶対に受講生さんに面倒向かって話さないので
本当に勘違いする人が後を絶ちませんね。
コメントありがとうございます。
「真面目にきちんと勉強してきた人が受験するのなら合格率がもっと高くなる」というのは本当にそうだと思います。医師国家資格などがその最たる例で、この例からも「合格率が高いから簡単」とか「合格率が低いから難しい」とは言えないことが分かります。
受験する側の勉強不足も確かにありますね。回によって準備不足の人の割合が大きく変動するということは考えにくいので、合格率の変動そのものの原因が準備不足だとは思いませんが、「簿記3級は簡単に受かる」などの世間の風説を鵜呑みにされていて、明らかに準備不足の方が多くいらっしゃいます。きちんと準備をして試験に臨めば、全体的に合格率は高くなると感じています。
記載されていることは間違いないです。
今から20年程前に日商簿記1級の合格4回しました。合格してるのになぜ4回合格したかというと、学校のエゴで各個人で受験料を負担させて受験させているというからくりです。そのため合格する人はほぼ毎回合格して、他の生徒も何度か受験してようやく合格するのです。では何故受験させるかというと、学校の合格率向上及び合格人数を増やすことにより、それだけこの学校に入学すると合格できますというアピールだということです。確かにその学校で勉強することにより、7割の生徒が合格して卒業することも事実です。そして、社会に出て何十年ですが、日商簿記1級合格者は3人しか記憶に無いです。
私が受験した日商簿記1級の試験で一番難しかったのは、平成4年又は5年の工業簿記の小数点が4桁まで求める試験だったと思います。受験生のほとんどがミスをして、全体合格率が1%以下だったということです。そのため、秋の試験は合格率調整で大量の合格者が生まれたことがあります。
合格率は10%というのは、あくまで年間2回の試験の合計に対する合格率だということです。そして、合格率というより複数の合格者が何度も受験していること。実質合格率は5%しかないのではと思います。
コメント、そして貴重な情報ありがとうございます。やはり簿記学校の都合があるのですね。
おっしゃるような簿記学校の裏話はいろいろと耳にするのですが、一生懸命簿記の勉強をしている人に不利益を与えるようなことを簿記学校がするのはいかがなものかと思っています。
何やらとんでもない回があった様ですね。
私が知る範囲では、過去問集で84回が1.9%と数字も酷く、更に全科目ひとクセある問題だったなと
後は95~98回の14.7→6.5→3.1%の酷いコンボで、受験生が悲惨と思ったし
コメントありがとうございます。
過去にはそういった回もありましたね。問題の難易度が高すぎると白紙の答案が多くなるのですが、白紙だとどのような傾斜配点を行っても0点になります。白紙の答案が多い科目が1科目でもあると、大部分の受験生が不合格になってしまい、そういったケースでは傾斜配点を使っても合格率を10%まで持っていけないようです。
ソースも何も無いので恐縮ですが、感覚として会計士受験生の8割が1級を受験して合格してるってのは有り得ないと思いますよ
会計士試験の大手予備校に通学してますが周囲を見渡してみてももっともっと落ちてます
上級生に限定してみても8割にはおそらく遠く及びません
コメントと貴重な情報ありがとうございます。
ここでの合格率の話なのですが、ひょっとすると合格率の計算方法に誤解があるかもしれません。この計算では「日商簿記1級に合格できなかった人の多くは公認会計士の受験を見送る」という前提が含まれています(初めて会計士試験を受ける人のうち1,000人の人が受験して、その合格率が80%ということなので、そういうことになります。)。
言い換えると「会計士の講座を受講されていても、簿記1級の出来が悪くて会計士試験の受験を見送った人」は「会計士受験生の1,000人」には含まれていないということになります。なので、「会計士受験生の簿記1級の合格率が80%」というよりも「20%の人は日商簿記1級が不合格でも会計士試験を受けている」と考えた方がいいのかもしれません(極端な例で恐縮ですが、「日商簿記1級の合格者だけが会計士試験を受験し、日商簿記1級の不合格者は全員会計士試験を受験しない」と仮定した場合、ここでいう合格率は100%になります)。記事の内容、分かりにくくてすみません。
とはいえ、「日商簿記1級に合格できなかった人の多くは公認会計士の受験を見送る」という前提が現在では変わっている可能性はあります。私が日商簿記を受験していた頃は、「会計士講座を受けている人で簿記1級に合格できなかった人」の大半は簿記1級に合格できるまでは簿記の勉強に集中して会計士試験は先送りしていたのです。
現在の状況を調査してみようと思います。
税理士・公認会計士・日商1級取得者は既に飽和状態です。金融庁は税理士・公認会計士の合格者数を削減しています。日商1級合格者も決して少なくありません。既に飽和状態に陥り、合格(取得)しても仕事が有ると云う保証は何処にも有りません。大企業を含む上場企業の多くは会計ソフトを既に導入していて、資格手当を支給する企業数は年々減少の一途を辿っています。合併・統廃合による人員整理も進み、経費削減で従業員の希望退職者を募集する企業も年々増えています。
コメントありがとうございます。
そうですね。資格自体のパワーは落ちている印象があります。合格しても仕事があるという保証は確かになくなってきました(公認会計士に若くして合格できればまず大丈夫ですが…)。経理の仕事自体もより進化する必要があると日々感じています。
約10年前に純粋な簿記1級の学習で、簿記1級に合格したものです。
O原に通っていましたが、講師から簿記の単科コース受講生の合格率は全国平均と
ほとんど変わらないと言われたことがあります。
私は午前午後と授業のある日曜クラスに通っていましたが、極端に合格率が低い時は
日曜クラスの合格者が0の時もあったそうです。
純粋な簿記1級受験生の合格率が低いのは、独学の受験者等が多いということでしょ
うか?
また、税理士講座の受講生の日商簿記1級合格率は、大体3,40%だと講師から聞き
ました。
2年間で簿記1級と簿財までいく人もいるそうですが、過半数は1級も取れずに講座
を修了するそうです。
税理士資格を取りたい人には、日商簿記1級よりも全経簿記1級を勧めているようで
すね。
薬剤師のような国家資格で、大学の専門の学部で勉強しないと取得できない資格試験
と比較するのは、ちょっと違うかなという気がします。
当然日商簿記1級よりも薬剤師の方がやらなければならないことが多いのでしょうか
ら、学習時間も長くなるし、多分実験等もあるのでしょう。
比較するのは、無理があるのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
約10年前に簿記1級に合格されたのですね。O原校の情報、参考になります。簿記学校の合格率に関する情報は本当に手に入りにくいので、ありがたいです(合格率を学校が公表することはほとんどないのです)。
O原校の講師によるO原校の情報なので多少高めに見積もられている可能性もありますが、それでも全国平均と変わらないというのは高いと思います。O原は数ある簿記学校の中でも評判もよいのでさすがだと感じます。
独学の受験者等が多いから純粋な簿記1級受験生の合格率が低いとは私は考えておりません。なぜかというと、簿記1級を独学で勉強をされる方は確かに多いのですが、たいていの方は途中で挫折されて受験までいかないからです。受験しないのであれば合格率には影響を与えません。
逆に独学で勉強されて受験まで持っていく方はかなり実力をつけていることが多く、通信や通学の方と比べても遜色ないと感じます。
純粋な簿記1級受験生の合格率が低いのは、単純に「会計士受験生や税理士受験生が簿記1級を受けているから」だと思います。簿記1級は合格率が10%程度に調整されるので、会計士受験生や税理士受験生が簿記1級を受ければ受けるほど純粋な簿記1級受験生が受かる「席」がなくなってしまいます。例えていえば、「高校生の大会に大学生が出場してくるから、高校生がほとんど勝ち残れない」というのと同じ感じです。
簿記1級の合格を目指す人は会計士受験生や税理士受験生もライバルだと考えなければならないということだと思います。
ちなみに、税理士受験生の合格率の件ですが、これらの数字は税理士試験の受験者数の情報から逆算して推定しているものになります。例えば、税理士受験生2,000人という数字は税理士簿記論の受験者数が約20,000人で、初受験者は約10%と推定して2,000人といった感じです(税理士試験は合格まで長期にわたる試験なので初受験者数は少なめに推定しています)。
つまり、「税理士受験を目指して簿記1級を勉強している人」であっても「簿記1級に不合格で税理士試験を受けなかった人」はこの「税理士受験生」には含まれていないのです(先ほどの20,000人に含まれていないからです)。なので、ここでいう60%というのは「税理士試験を受けた人の中でその時期の簿記1級に合格した人の割合」という意味合いになります。
この表は「税理士試験を目指している人は日商簿記1級に60%合格している」と読むのではなく、「税理士試験を受験している人が1,200人簿記1級の合格者に含まれている」と読む方が正確だと思います。分かりにくい書き方になっていてすみません。
薬剤師との比較の件ですが、私も比較するつもりはありません。薬剤師や医師国家資格の例は「合格率で試験の難易度を比較する意味がない例」としてあげさせていただいています。
貴重な情報ありがとうございました。参考にさせていただきます。
確かに会計士受験生、税理士受験生の存在は1級受験生にとっては
脅威だし強敵だと思います。
しかし、仮に1級の問題が非常に易しくて答案提出者の50%が70点を
大きく超えて9割取ったとします。その場合、合格率を10%に調整する為に
税理士試験、会計士試験みたいに95点をボーダーにしたりするのでしょうか?
巷では、日商1級は競争試験だとか合格率を10%にするために調整しているだとか
いろいろ言われてますが、受験生の方々の出来が非常に良ければ合格率50%はおろか
合格率100%もありうると思います。要するに、日本商工会議所も そこまで
意地悪はしてこないはずです。
コメントありがとうございます。
匿名さんのお考えはもっともで、表向きはそのようになっています。しかし傾斜配点は間違いなく行われていると思われます。「答案提出者の50%が70点を大きく超えて9割取った」場合、その不正解の1割に多くの配点を割り当てて点数を下げ、10%の人が7割程度の点数になるように配点が調整されるはずです。なので「95点がボーダーになる」のではなく、「70点がボーダーになるように点数が与えられる」といえます(配点は公表されないのでこのようなことが可能になります)。
日商簿記の歴史は長いので、これまでには問題が非常に易しかったり受験生が優秀だったりしたこともあったはずです。しかし、私が知る限り日商簿記1級の合格率が15%を超えたことはありません。私がこのように考える根拠の一つです。
もし合格率が50%を超えることがあるとすれば、それは「50%以上の受験生が全ての解答欄を完答した場合」だけだと思います(全ての解答欄を完答されると、どのような配点にしても満点になるので、傾斜配点も無意味だからです)。
こんな長文書いて暇スギィ!
コメントありがとうございます。この記事は長文ですが結構お読みいただけているのでありがたいです。
日商検定の闇を思うことが多くなりました。
検定試験の目的って何でしょうか。
国民にとって、簿記の知識を啓蒙し、企業、地域で活躍する有為な人材の輩出にあるはずです。選抜や競争試験でないはずです。それを合格率の低さで、見栄を張り、価値を見出すような次元の低さ、呆れます。
法律系国家試験ならわかりますよ。でも「検定試験」です。日商の見栄で試験をやられたんじゃかないません。
最近の試験を俯瞰すると、その目的がおかしな方向に向かっているようで心配です。
これからAIの進展で税理士の仕事は無くなる方向や、簡易ソフトでも容易に決算整理できてしまうご時世で、もはや電卓を叩いて、計算する簿記検定が化石化したものになっていくようです。
ITを中心にしたスキル向上のための簿記検定にして、その合格率も5割くらいにならないのかと思います。
簿記1級の闇、傾斜配点、もうやめてもらいたいです。指導者説明会でも、申し入れしても馬耳東風のようですし、日商の頑固な意思を感じますね。
コメントありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。検定試験で合格者数を絞る正当性はありません。受験生が優秀な回は合格者が多く、そうでなければ少なくていいと思います。この点は「簿記1級に合格することで税理士試験の受験資格が得られる」という点と無関係ではないかもしれません(税理士試験は明らかに合格者数をコントロールしていますので……)。
ただ、その税理士試験ではかなり試験傾向が変わってきていて、簿記論では集計力よりも基本的な内容の確実な理解が試される問題になってきています。財務諸表論も暗記から理解、思考が重要な出題になってきています。簿記おやじさんがおっしゃるようにただの知識は検索すれば手に入りますし、ただの計算(集計)は会計ソフトがやってくれます。この点を会計士試験や税理士試験の試験委員の方もちゃんと認識しているのは間違いなく、簿記検定も徐々に変わっていくといいなと思っています。
コロナ禍の2020.11月試験で合格しました。私は約10年前に税理士試験の簿財に合格しており、転職したく仕事を辞め、勉強し直しと原価計算の学習のため1級を受験、運良く1度で合格でき転職もできました。知人も昔、簿財の合格後に、過去に落ちた1級を受け直し合格していました。
私は1級の合格を目的に勉強開始しましたが、まれに居る我々のような方や対策無しでも合格ラインに達する公認会計士試験の受験生たちが1級合格者に多数居る事は、よく知っていました。そのため私はLECの公認会計士講座で簿記の連結関係と管理会計を中心に4ヶ月半ほど勉強しました。試験対策まで出来ず、無対策でした。
そのまま短答式も論文式も突破する気合いで勉強しましたが、私の頭では正直、1級を確実に合格できるレベルまで練り上げようとすると1年はかかるなと頭を抱えました。結果的に出題にうまく対応でき合格できましたが、1級を目指して1級に合格した以前の職場の方は、やはり私よりずっと優秀な方だったんだなと確信しました。旧帝大卒のその方でも、2回落ち3回目にやっと合格できた、と言っておりましたが…汗
税理士試験の受験生の減少に歯止めがかからない中で、簿記が見直される事を期待いたします。
コメントありがとうございます。
本当に簿記1級の合格者の中に会計士受験生や税理士受験生(やまだたろうさんのように過去に合格された方も)が多いと感じます。
私も簿記が見直されてほしいと思っています。
平野様 お久しぶりです。(メールアドレスで平野様に身元が伝わると良いのですが。)
第165回の試験で合格となりました。
以上です。
ご連絡ありがとうございます(メールアドレスで氷雨さんがどなたか分かりました)。お久しぶりです。
簿記の勉強、続けられていたのですね。合格おめでとうございます。お役に立てて嬉しいです。