- 簿記を勉強しても時間がたつとすぐに忘れてしまうんだけど……
- 簿記を効果的に身につける方法が分からない
- 簿記を忘れることの対策について教えて!
簿記を勉強しても時間がたてば忘れてしまって、いくら勉強しても知識が増えていっている気がしないと悩んでいる方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん忘れる量を少なくして、どんどん前に進む方法も熟知しています。
この記事では、覚えずに身につけるために知っておくべき脳のメカニズムと忘れない勉強法について解説します。
この記事を読めば簿記の勉強を効果的に進めることができるようになって簿記の勉強が楽しくなります。
結論を一言で言うと、「基本問題に多くの力と時間を使うこと」「翌日の復習は絶対に行うこと」「翌日以降も定期的に復習すること」で忘れてしまう量を減らすことができます。
覚えずに身につけるための勉強法

記憶に関する有名な研究に次の2つがあります。
- エビングハウスの忘却曲線(Wiki)
- レミニセンス現象(Wiki)
エビングハウスの忘却曲線から考える復習のタイミングとポイント
エビングハウスの忘却曲線といわれるものがあります。エビングハウスの実験によると、全く無意味な音節は、次のような形で忘れていくという結果が出ています。
- 20分後には、42%を忘れる
- 1時間後には、56%を忘れる
- 1日後には、74%を忘れる
- 1週間後には、77%を忘れる
- 1ヶ月後には、79%を忘れる
勉強の仕方を考えるとき、エビングハウスの実験の結果から読み取るべきことは、次の2つです。
- 全く無意味な言葉は1日でほぼ4分の3を忘れる(体系的な知識はもっと緩やかに忘れると推測できます)
- 1日で急激に忘れ、その後はゆるやかに忘れていく
エビングハウスの忘却曲線から、最初の1日を忘れずに過ごせれば、それ以降はあまり忘れないということが推測できます。そこで、最初の復習は翌日に行います。
また、「無意味な言葉は1日で4分の3を忘れる」ということは、もし理解せずに丸暗記を行った場合、翌日の復習では同じ問題を解いても解けないと考えられます。
そこで、翌日の復習は、丸暗記に走ってしまっていないかを確認するために行います。
そもそも勉強したはずのことを次の日にできなくなっているということは理解が浅いということです。
次の日の復習で問題が解けなかった場合は、丸暗記に走ってしまっている可能性が高いと考えて、再び理解を深めます。
レミニセンス現象から考える復習のタイミングとポイント
レミニセンス現象とは、あることを覚えた時、覚えた直後よりもある程度時間が経った後の方が思い出しやすくなる現象のことです。
人間の脳はある程度の時間をかけて記憶を育てるワインのような性質があるということです。
レミニセンス現象から、復習のタイミングはある程度の時間が経った後がいいということが分かります。
毎日復習を続けることは効率的ではありません。しかし、間隔を空けすぎて忘れてしまっては復習になりません。初めての学習と同じになってしまいます。
エビングハウスの忘却曲線とレミニセンス現象を合わせると絶妙のバランス感覚が要求されますが、あまり神経質になっても仕方ありません。
最低限、次の復習日がすぐに分かるくらいの分かりやすさも必要です。
忘却曲線とレミニセンス現象から考える理想的な復習のタイミング
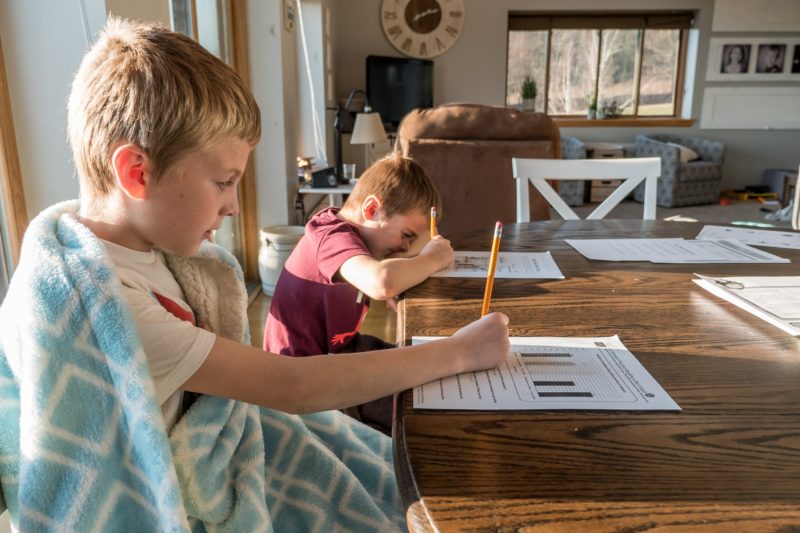
忘却曲線・レミニセンス現象・分かりやすさの3つを全て満たす復習のタイミングを考えると、次の間隔で復習していくのが極めて合理的だと考えられます。
- 1回目の復習…翌日
- 2回目の復習…その1週間後
- 3回目の復習…その2週間後
- 4回目の復習…その1ヵ月後
復習のタイミングはこれを目安に微調整してみてください。また、時間がない場合は復習回数が少ないものから優先的に復習するようにしてください。
エビングハウスの忘却曲線から、1回目の学習から時間がたったものほど忘れにくいということが読み取れるからです。
復習回数が少ないということは、それだけ1回目の学習から時間がたっていないため、より忘れやすいのです。
適切なタイミングでしっかりと復習を繰り返していくことで、自然と忘れずに身につけていくことができます。覚えようとしなくても忘れないのです。
「覚えようとしなくても忘れない」という感覚をできるだけ早くつかんでおくと、簿記の勉強がどんどん楽しくなっていきます。
忘れないための復習は問題を解くだけで大丈夫
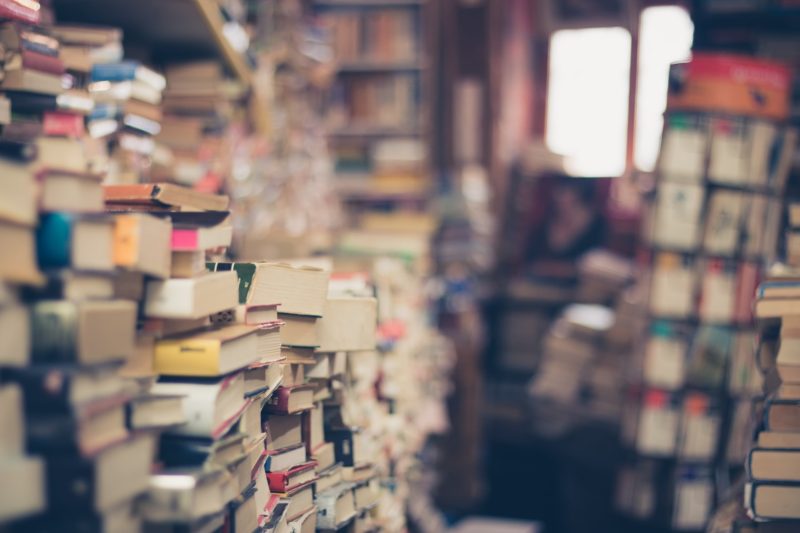
復習では問題を解くだけで大丈夫です。特にテキストを読む必要はありません。
復習では2つの効果が期待できます。1つは今確認した「自然と忘れずに身につけること」です。もう1つは「無意識レベルで問題が解けるようになること」です。
「自然と忘れずに身につけること」については「簿記の基本が完璧に身についた状態とは…」で詳しく解説しています。
「無意識れ別で問題が解けるようになること」については「無意識でできるレベルまで持っていかなければならない理由」で詳しく解説しています。
無意識のレベルにもっていくためには、ひたすらに反復練習を行うことが必要です。反復練習は同じ問題を複数回解くことを意味するのですが、ここで行う復習が反復練習にもなります。
忘れないためには基本問題を繰り返すことが大切

問題集などでは、たいてい「基本→応用→実践→過去問」や「例題→類題→演習→過去問」のように、難易度が順に上がっていく構造になっています。
「基本→応用→実践→過去問」という形で順番どおりにやる必要はありません。最も力を注ぐべきは「基本」であり「例題」です。
「基本」「例題」に力の9割を注ぎます。「基本」「例題」だけは誰にも負けないくらい練習するのです。
何度も反復を行い、無意識レベルに持っていきます。無意識レベルまで持っていけば、応用問題や過去問さえも特に難しいと感じることなく解くことができるようになります。
どうしても暗記しなければならない場合の暗記法
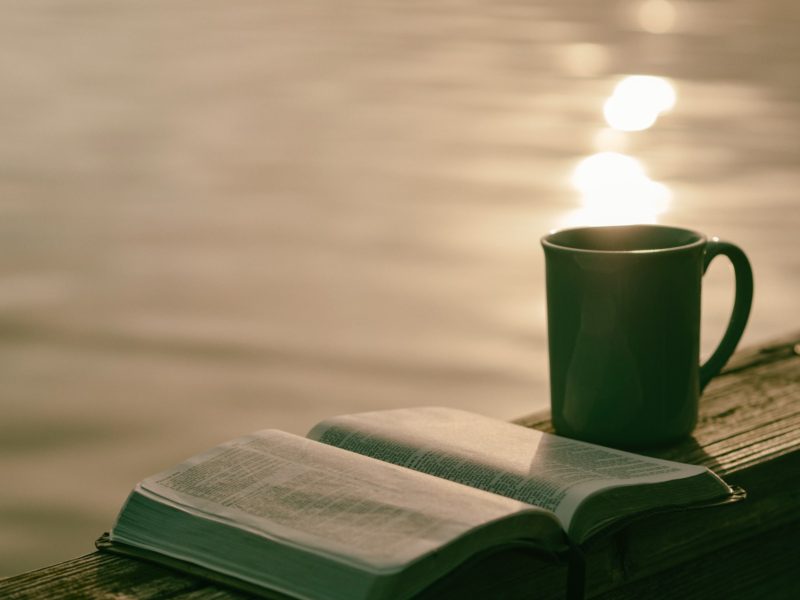
意識的な丸暗記はしないことが大切です。しかし、例外的に暗記しなければならない部分もわずかですがあります。
そういった暗記を行う場合には次のような方法で行うと効率的です。
- 暗記は細切れ時間に行う
- 寝る前にもう一度確認する
- 起きたらすぐに確認する
1.暗記は細切れ時間に行う
暗記を行う場合は「テレビのコマーシャル中」「トイレ中」「電車の待ち時間」などを使うと効率がいいです。1分程度の時間にも暗記はできるので、こうやって暗記するのが効率的です。
また、それほど「暗記しよう」と強い意志を持って暗記することもありません。
「すき間時間に覚えているんだから、覚えられれればもうけもの」的な感じで余裕を持ってすることが大切です。
2.寝る前にもう一度確認する
空き時間の中で見た内容は必ず暗記した日の寝る前に復習することが大切です。記憶は寝ているときに整理されるので、寝る前に覚えるのが効果的だからです。
3.起きたらすぐに確認する
記憶は繰り返すことで強化されます。忘れないためには1回目の復習はすぐに(翌日に)行うことが大切なので翌日の朝にもう一度確認しておきましょう。
そして、もし覚えていなければ次の空き時間にもう一度勉強すれば大丈夫です。
【まとめ】簿記を忘れる最大の対策は覚えようとしないこと

翌日の復習は絶対に行い、丸暗記に走ってしまっていないか確認することが大切です。
復習は次の間隔で行うのが理想的です。
- 1回目の復習…翌日
- 2回目の復習…その1週間後
- 3回目の復習…その2週間後
- 4回目の復習…その1ヵ月後
問題練習は基本問題に多くの力と時間を使うことが大切です。また、どうしても暗記しなければならないものは隙間時間に行い、寝る前と起きてすぐに確認する。
- 弊社が運営している【簿記革命】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに日商簿記の合格を目指して勉強したい方は【簿記革命】をご検討ください。
- 簿記を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法」で詳しく解説しています。

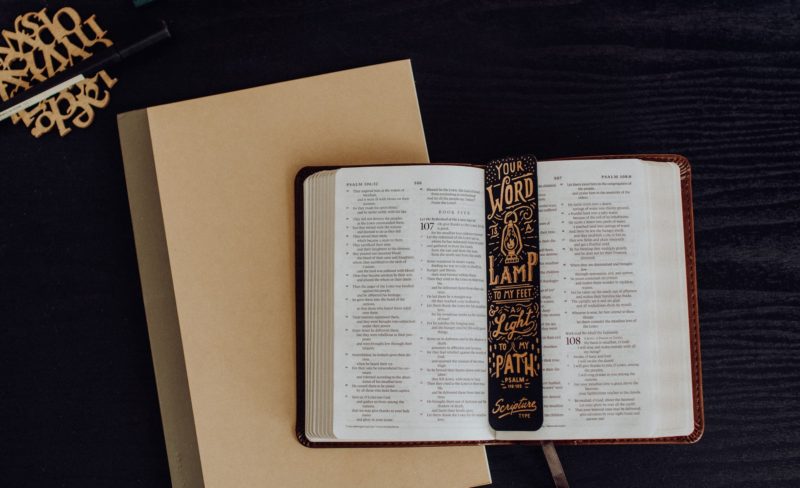
コメント
個人的な考えですが目的意識をもって身に付けることと早い段階での復習が重要だと思います。
100%忘れてからでは同じことの繰り返しであまりにも効率の悪い勉強になり勉強すること事態が「苦」になってしまいますので・・・
「簿記奮闘記」テーマのブログも更新できるように頑張ります!!
おっしゃるとおりだと思います。完全に忘れてから復習するのは最初からのやり直しになるのでつらいですよね。最初の復習は翌日がベストかなと感じています。
「簿記奮闘記」の更新がんばってください。
初めてのコメントです!
私は今1級を独学で勉強しています。
基礎をガッチリ固めようとしているのですが、
テキストを読む→例題を解く→問題演習
と進めています。
ただ、ひとつ気になるのが、基本の問題を解く数が足りてないんじゃないか?ということです。
何冊も問題集を買うわけにもいきませんし…。
2級のときは、理解に苦しむ問題があるときは、同じテキストの同じ問題を何度も繰り返し解いていた(例えば精算表で特商の仕訳につまずいたときは、特商の基本仕訳の問題
を何度も解く)のですが、
その勉強方法を続けて良いのでしょうか??
それとも全く同じ問題より、違う問題を多数解いた方がいいのでしょうか??
わかりにくくて申し訳ありませんが、もし良ければ教えていただければと思いますm(_ _)m
コメントありがとうございます。
簿記1級は簿記2級に比べて難易度も試験範囲の広さも急激に上がるので、不安も大きいと思います。
しかし、サニーさんが簿記2級でされていた勉強方法が正解です。簿記1級でも簿記2級のときと同じように同じ問題を繰り返し解いてください。
解く回数の目安ですが、1回目から正解できた問題でも最低3回、そうでなければ6回くらい解く必要があります。簿記1級の全範囲は、商業簿記・工業簿記合わせれば問題集は6
冊くらいになります。この6冊を、繰り返し繰り返し同じ問題を解いてください。
また何かあればコメントください。サニーさんの簿記1級の勉強、応援しています。