- 受験予定日までに学習範囲をやり終えることができるか不安
- 勉強は進めているけど、勉強した内容が身についていない気がする
- 勉強時間をどのように捻出したらいいか分からない
簿記3級に合格するためには自分に合った勉強スケジュールを立てることが不可欠ですが、どのように計画を立てたらいいのか分からずに悩んでしまう方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん勉強スケジュールの立て方にも精通しています。
この記事では簿記3級の勉強スケジュールを立てるコツ、自分に合った勉強スケジュールを立てるときに意識すべきポイントについて解説します。
この記事を読めば試験日までの時間を最大限効果的に使うための勉強計画を立てることができるようになります。
結論を言うと、 自分に合った勉強計画を立てるためには「自分の体調や仕事の繁忙期を意識する」「前日の夜か当日の麻にざっくりと計画を立てる」「1日の中の隙間時間を有効活用する」の3つを意識して下さい。
簿記3級の試験日までの大まかな勉強スケジュールを立てる

簿記3級の勉強をする場合、簿記3級を最終目標にするのか、それとも簿記2級以上を目指すのかで簿記3級を勉強する時間が変わってきます。
簿記2級以上を目指すのであれば、簿記3級は95点以上得点できる実力を身につける必要があります。そのため、必然的に多くの勉強時間が必要になるのです。
日商簿記3級までで十分なのであれば「勉強時間は88時間、勉強期間は2~2.5ヶ月」、日商簿記2級以上を目指すのであれば、「勉強時間は108時間、勉強期間は3~3.5ヶ月」を目安にしてください。
簿記3級の勉強時間については「【日商簿記3級の勉強時間】社会人は何か月?【1ヶ月は?】」で詳しく解説しています。
自分の体調や仕事の繁忙期を確認する
勉強スケジュールを立てる場合、最初に「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」を把握しておくことが大切です。
そして、「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」は新しく進む勉強量を少なめにすることが大切です。このような勉強スケジュールを立てることで「試験日までに間に合わないリスク」を激減させることができます。
試験日までの大まかな勉強スケジュール3パターン
これから勉強スケジュールのパターンを3つお伝えします。どれかに決める必要も、どれかを選ぶ必要もありません。この3パターンはあくまでも出発点です。
「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」を踏まえた上で、これらのパターンを調整してあなただけの勉強スケジュールを立ててください。
平均型:「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」が特にない人におすすめ
「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」が特にないのであれば「平均型」を出発点に勉強スケジュールを立てることをおすすめします。平均型の場合、平日5日間、ずっと同じペースで新しい内容に入っていきます。
私が運営している簿記通信講座である【簿記革命3級】の場合、問題が74問あります。平日5日間、1日2問ペースで新しい内容に入ります。8週間で問題集をやり終え、その後の2週間で過去問練習(平日5日間、1日1回分)を行います。
この勉強スケジュールを出発点に、使っているテキストと問題集に合わせて調整してください。
スタートダッシュ型
「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」が試験日近くにやってくるのであれば「スタートダッシュ型」を出発点に勉強スケジュールを立てることをおすすめします。
また、「スタートダッシュ型」は精神的にも余裕ができる方法なので、試験日までに終わるかどうか心配になりやすいのであれば「スタートダッシュ型」がおすすめです。
「スタートダッシュ型」では勉強期間の後半に勉強量を減らすことに備えて、最初に勉強量を増やしておきます。
私が運営している簿記通信講座である【簿記革命3級】の場合、問題が74問あります。前半は平日5日間、1日3問ペースで新しい内容に入ります。「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」には平日5日間、1日1問ペースで新しい内容に入ります。
6週間ほどで問題集をやり終え、その後の4週間で過去問練習(平日5日間、2日で1回分)を行います。
この勉強スケジュールを出発点に、使っているテキストと問題集に合わせて調整してください。
スロースタート型
「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」が勉強期間の前半にやってくるのであれば「スロースタート型」を出発点に勉強スケジュールを立てることをおすすめします。
スロースタート型は最後に追い上げる形になるので、そういった勉強が性に合っているのであれば「スロースタート型」がおすすめです。しかし、スロースタート型で勉強すると急なアクシデントに対応することが難しくなるので、その点には注意する必要があります。
「スロースタート型」では勉強期間の前半に勉強量を減らして最後に追い上げます。
私が運営している簿記通信講座である【簿記革命3級】の場合、問題が74問あります。前半の「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」は平日5日間、1日1問ペースで新しい内容に入ります。学習期間の後半には平日5日間、1日3問ペースで新しい内容に入ります。
8週間ほどで問題集をやり終え、その後の1週間で過去問練習(平日5日間、1日で2回分)を行います。
この勉強スケジュールを出発点に、使っているテキストと問題集に合わせて調整してください。
前日の夜に次の日の勉強スケジュールを立てる

試験日までのざっくりとした勉強スケジュールを立てたら、次に毎日の具体的な勉強計画を立てます。
まずは前日の夜に翌日の予定を30分刻みで計画を立てます。次の流れで計画を立ててください。
- 「絶対に勉強できない時間」を斜線で消してください
- 残った部分に「勉強」と「息抜き」を割り当ててください
- 計画と実践を繰り返すことで、改善を続けてください
1.「絶対に勉強できない時間」を斜線で消してください
1日の計画を立てるため、「30分刻み、48目盛りの横棒グラフ」を作ります。そして、「睡眠」「仕事」など、絶対に勉強できない時間を斜線で消します。
一般的に、睡眠時間で7時間、仕事で8時間を斜線で消すことになります。
2.残った部分に「勉強」と「息抜き」を割り当ててください
斜線で消されずに残った部分を「勉強」と「息抜き」に割り当てます。
詳しくはこれからお伝えしますが、簿記は電卓を使って問題を解く時間が必要なので、「机の前に座る時間」を1時間ほど確保する必要があります。
「机の前に座ることができる時間」を「息抜き」に使うのは最小限にしてください。
「多い日で2時間」「少ない日で1時間」の平日の勉強時間を確保してください。
3.計画と実践を繰り返すことで、改善を続けてください
1と2を毎日行っていると「この時間は勉強できないと思っていたけれど勉強できる」「この時間は勉強できると思っていたけれど勉強できない」といったことに気づきます。
そのたびに改善していくことで勉強スケジュールの計画を立てること自体も上手になっていきます。
1日の勉強スケジュールの具体例
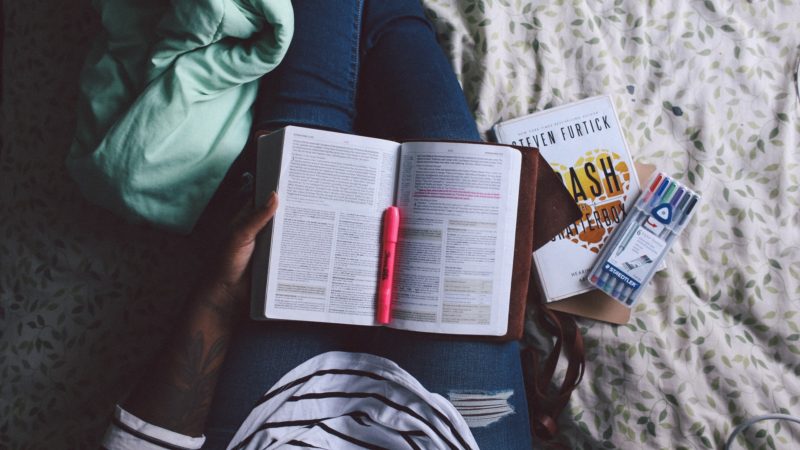
簿記は問題練習が非常に大切です。しかも、1回解いたらそれで終わりにするのではなく、最低3回繰り返す必要があります。
具体的には次のタイミングで3回解きます。
- 1回目(当日)
- 2回目(1回目の翌日)
- 3回目(2回目の1週間後)
また、簿記3級を勉強している時期は電卓操作に慣れていないので、ウォーミングアップに電卓練習もしておくことをおすすめします。
電卓練習については「電卓練習用計算問題(早打ち練習に最適)【無料プリントあり】」で詳しくお伝えしています。
つまり、1日に勉強する内容は全部でこれだけあります(時間は目安です)。
- 電卓練習:10分
- 新しい内容(テキスト2問分):30分
- 新しい内容(問題練習2問分):20分
- 前日の復習(問題練習2問分):15分
- 1週間前の復習(問題練習2問分):15分
この勉強内容をどのように1日で勉強していくのか、「まとまった時間(2時間以上)が取れる場合」と「まとまった時間が取れない場合」に分けて、それぞれ具体的にお伝えします。
1日にまとまった時間(2時間)が取れる場合
1日にまとまった時間を2時間取れる日は、「1日に勉強する内容」を次の順番で行います。
- 電卓練習
- 前日の復習
- 1週間前の復習
- 新しい内容(テキスト→問題集)
作業興奮を利用するために、最初に電卓練習を行います。
その後、負担が小さい順番で取り組んでいくことで、無理なく勉強を進めることができます。「25分勉強するごとに5分休憩する」というペースで勉強を進めることが大切です。
1日にまとまった時間(2時間)が取れない場合
まとまった時間を2時間取れない日は、細切れの時間を活用する必要があります。
簿記3級であれば、「机の前に座って勉強する時間」を60分、「それ以外の隙間時間」を30分、確保してください。そして、確保した時間を次の形で効率よく勉強にあててください。
朝の30分:電卓練習と前日の復習
起床直後はまだ頭が起きていないので、新しい内容の勉強するのは大変です。「朝の30分」では目を覚ますのに効果的な「電卓練習」と比較的負担の小さい「前日の復習」を勉強するのがおすすめです。
通勤時間の30分:新しい内容をテキストでインプット
通勤中の電車やバスの中では机が使えません。テキストを読むのに最適です。
昼休みの30分:1週間前の復習
昼休みは気が散りやすいので新しい内容の勉強をするのは少し大変です。「朝の30分」でできなかった復習の残りを勉強するのがおすすめです。
もし集中できるのであれば新しい内容の問題練習を行っても大丈夫です。
帰宅後の30分:新しい内容の問題練習
帰宅後は後の予定がないので、集中して新しい内容の問題練習を行うのに最適です。
こういった形で勉強時間を確保することで、無理なく勉強していくことができます。
【簿記3級】あなたに合った勉強スケジュールの具体的な立て方
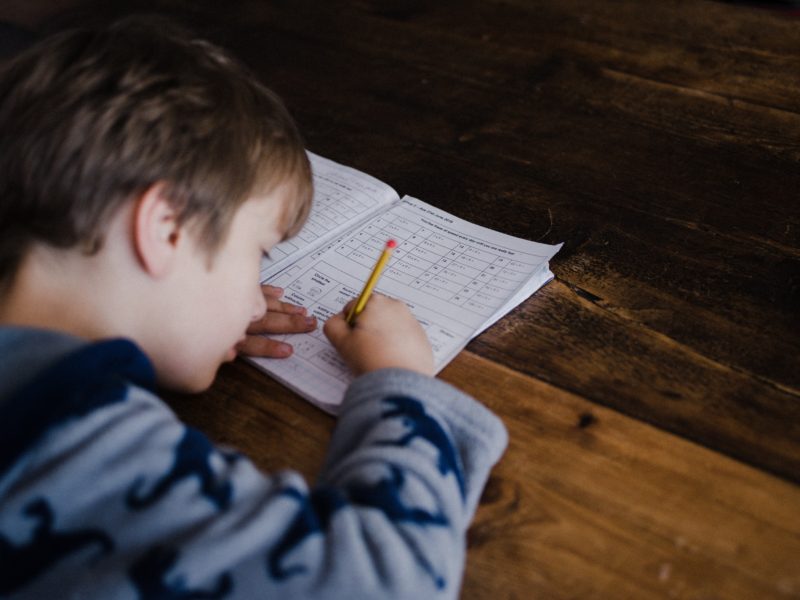
簿記3級の勉強時間の目安は108時間、勉強期間は3~3.5ヶ月です。この勉強時間を念頭に勉強スケジュールを立てる必要があります。
最初に「体調を崩しやすい時期」や「仕事が忙しくなる時期」を把握しておきましょう。そのような時期には新しい内容に入る量を減らします。
試験日までのざっくりとした勉強スケジュールを立てたら、次に毎日の具体的な勉強計画を立てます。次の日の具体的な勉強計画を前日の夜に立てます。
まとまった時間を2時間取れる日は、次の順番で勉強します。
- 電卓練習
- 前日の復習
- 1週間前の復習
- 新しい内容(テキスト→問題集)
まとまった時間を2時間取れない日は、次のように細切れ時間を活用します。
- 朝の30分:電卓練習と前日の復習
- 通勤時間の30分:新しい内容をテキストでインプット
- 昼休みの30分:1週間前の復習
- 帰宅後の30分:新しい内容の問題練習
簿記3級を勉強しているあいだに勉強スケジュールの立て方も身につけることで、簿記2級以降の勉強も効果的に進めることができます。


コメント