- 簿記を勉強していると税効果会計っていう内容が出てくるんだけど……
- 税効果会計がどういう取引なのか難しすぎて分からない
- 簿記2級の税効果会計の仕訳を教えて!
税効果会計は2017年度までは簿記1級で学習していた内容で、非常に難易度が高いです。そういった理由から、税効果会計を苦手にしてしまっている人は非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん税効果会計にも熟知しています。
この記事では簿記2級で出題される税効果会計の仕訳についてわかりやすく解説します。
この記事を読めば税効果会計についての理解が深まるので、簿記2級で税効果会計の問題が出題されても自信を持って解答できるようになります。
結論を一言で言うと、税効果会計では、法人税等の前払いにあたる金額を繰延税金資産として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を減少させます。
法人税等の未払いにあたる金額は繰延税金負債として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を増加させます。
税効果会計で登場する勘定科目

最初に税効果会計で登場する勘定科目で特に難しいもの、なじみがないものについて解説します。
簿記2級で出てくる勘定科目の中で特に難しいのは次の3つです。
- 繰延税金資産
- 繰延税金負債
- 法人税等調整額
繰延税金資産とは:将来の税金の支払いを減少させる権利
将来の税金を前払いした場合に使う勘定科目が繰延税金資産です。将来の税金を前払いしたということは将来に支払う税金が減るということなので資産の勘定科目になります。
繰延税金資産は前払金の税金バージョンの勘定科目と考えると分かりやすいです。
前払金については「【簿記】前払金とは【仕訳と勘定科目をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
繰延税金負債とは:将来の税金を支払う義務
当期に負担すべき税金を未払いにした場合に使う勘定科目が繰延税金負債です。
現在の税金が未払いということは未払いにした分を将来に支払う義務が発生するということなので、繰延税金負債は負債の勘定科目になります。
繰延税金負債は未払金の税金バージョンの勘定科目と考えると分かりやすいです。
未払金については「【簿記】未払金とは【仕訳と勘定科目をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
法人税等調整額:税効果会計によって調整された法人税等
税効果会計を適用することで、当期に負担すべき法人税等の金額が変動します。
この「法人税等の金額の変動分」を意味する勘定科目が「法人税等調整額」です。「法人税等」に「法人税等調整額」を加減することで「会計上当期に負担すべき法人税等」の金額が分かります。
税効果会計の仕訳【簿記2級】
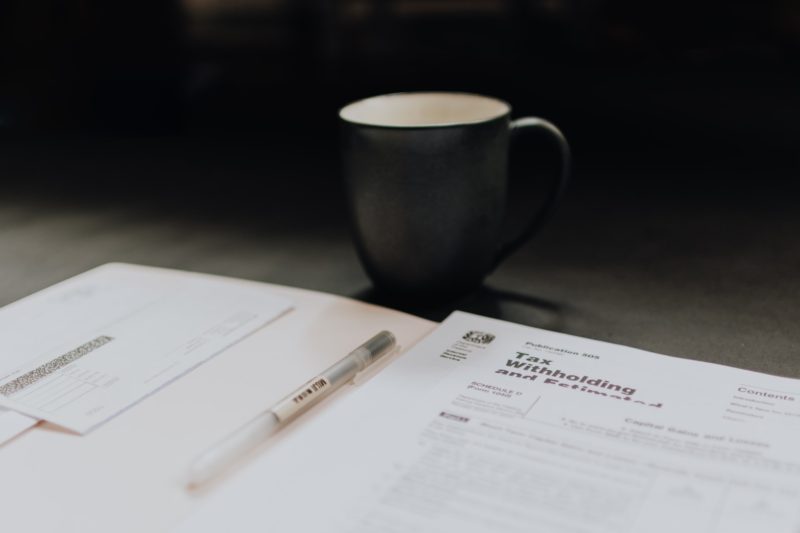
税効果会計を適用する場合、法人税等を前払いしている場合には法人税等の前払いにあたる金額を繰延税金資産として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を減少させます。
逆に法人税等の未払いがある場合は法人税等の未払いにあたる金額を繰延税金負債として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を増加させます。
税効果会計の仕訳の具体例【簿記2級】

貸倒引当金の損金算入限度超過
貸倒引当金を100,000円計上したが、税務上の貸倒引当金繰入限度額は70,000円である。そこで、損金算入限度超過額は税務申告で損金不算入とした。なお、法定実効税率は40%とする。
この例題をもとに税効果会計を適用するための仕訳を考えてみましょう。
税効果会計を適用するための仕訳を考える前に、貸倒引当金を計上する仕訳を考えておきましょう。『(借)貸倒引当金繰入額100,000』『(貸)貸倒引当金100,000』となります。
ここから税効果会計を考えます。
貸倒引当金の損金算入限度超過額は(貸倒引当金100,000円-貸倒引当金算入限度額70,000円=)30,000円です。
貸倒引当金の損金算入限度超過額は税務上の損金として認められず損金不算入となっているので、損金が30,000円減ることになります。
損金が30,000円減ることで課税所得が30,000円増えています。この結果、課税額が(増加した課税所得30,000円×法定実効税率40%=)12,000円増えています。
この増加した課税額12,000円は会計上の税引前当期純利益とは対応しない法人税等です。
会計上の税引前当期純利益とは対応しない法人税等なので法人税等から控除する必要があります。
法人税等を調整する勘定科目は「法人税等調整額」を使います。法人税等は借方に計上されているので、この法人税等から控除する意味の法人税等調整額は貸方となります。
よって『(貸)法人税等調整額12,000』となります。
この12,000円は実際に貸倒れが発生したときに税金の支払額が減少することで回収されます。
よって将来税金を減らす性質がある資産である繰延税金資産という勘定科目を使って『(借)繰延税金資産12,000』となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 12,000 | 法人税等調整額 | 12,000 |
減価償却費の損金算入限度超過
減価償却費を100,000円計上したが、税務上の減価償却費の損金算入限度額は70,000円である。そこで、損金算入限度超過額は税務申告で損金不算入とした。なお、法定実効税率は40%とする。
この例題をもとに税効果会計を適用するための仕訳を考えてみましょう。
税効果会計を適用するための仕訳を考える前に、減価償却費を計上する仕訳を考えておきましょう。『(借)減価償却費100,000』『(貸)減価償却累計額100,000』となります。
ここから税効果会計を考えます。
減価償却費の損金算入限度超過額は(減価償却費100,000円-減価償却費の損金算入限度額70,000円=)30,000円です。
減価償却費の損金算入限度超過額は税務上の損金として認められず損金不算入となっているので、損金が30,000円減ることになります。
損金が30,000円減ることで課税所得が30,000円増えています。この結果、課税額が(増加した課税所得30,000円×法定実効税率40%=)12,000円増えています。
この12,000円は会計上の税引前当期純利益とは対応しない法人税等です。
会計上の税引前当期純利益とは対応しない法人税等なので法人税等から控除する必要があります。
法人税等を調整する勘定科目は「法人税等調整額」を使います。法人税等は借方に計上されているので、この法人税等から控除する意味の法人税等調整額は貸方となります。
よって『(貸)法人税等調整額12,000』となります。
この12,000円は将来減価償却費の損金算入限度額として認められたときに税金の支払額が減少することで回収されます。
よって将来税金を減らす性質がある資産である繰延税金資産という勘定科目を使って『(借)繰延税金資産12,000』となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 12,000 | 法人税等調整額 | 12,000 |
その他有価証券の仕訳(全部純資産直入法)の具体例(税効果会計あり)

税効果会計を適用しない場合の「その他有価証券の仕訳(全部純資産直入法)」については「その他有価証券【仕訳と勘定科目をわかりやすく】」で詳しく解説しています。
その他有価証券の購入
その他有価証券を8,000,000円現金で購入した。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
現金8,000,000円で購入したので『(貸)現金8,000,000』、その他有価証券を購入したので『(借)その他有価証券8,000,000』となります。税効果会計は特に関係ありません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 8,000,000 | 現金 | 8,000,000 |
決算
決算となった。なお、その他有価証券の時価は9,000,000円であった(全部純資産直入法)。なお、税効果会計を適用し、法定実効税率は40%とする。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
その他有価証券は時価評価するので、帳簿価額を時価に修正します。帳簿価額は8,000,000円、時価は9,000,000円なので、帳簿価額を1,000,000円加算します。
よって『(借)その他有価証券1,000,000』となります。
次は貸方です。その他有価証券の評価差額は損益ではなく純資産に直接計上します。
ただし、税効果会計を考慮する場合は、全額を純資産には計上しません。評価差益のうち40%は将来税金として支払わなければならないからです。
評価差益1,000,000円のうち40%である400,000円は将来税金として支払わなければならない金額なので繰延税金負債として処理します。よって『(貸)繰延税金負債400,000』となります。
また、残りの600,000円は純資産に直接計上するので「その他有価証券評価差額金」を使います。よって『(貸)その他有価証券評価差額金600,000』となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 1,000,000 | その他有価証券評価差額金 繰延税金負債 | 600,000 400,000 |
収益や費用に全く影響していないので法人税等調整額も登場しない点がポイントです。
翌期首
翌期首となった。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
その他有価証券は洗替方式で処理するので、翌期首には決算整理仕訳の逆仕訳を切ります。税効果会計を適用していても同じです。
よって『(借)繰延税金負債400,000』『(借)その他有価証券評価差額金600,000』『(貸)その他有価証券1,000,000』になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 | 400,000 600,000 | その他有価証券 | 1,000,000 |
その他有価証券の売却
その他有価証券を8,500,000円で売却し、代金は現金で受け取った。
この例題の仕訳を考えてみましょう。
その他有価証券を売却したので帳簿価額を減額します。帳簿価額は洗替方式によって取得原価である8,000,000円になっています。これを減額するので『(貸)その他有価証券8,000,000』となります。
また、代金8,500,000円は現金で受け取っているので『(借)現金8,500,000』となります。
貸借差額500,000円はその他有価証券を売却したことにより発生した利益です。よって『(貸)その他有価証券売却益500,000』となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 8,500,000 | その他有価証券 その他有価証券売却益 | 8,000,000 500,000 |
【まとめ】税効果会計とは【簿記2級の仕訳をわかりやすく】

税効果会計を適用する場合、法人税等を前払いしている場合には法人税等の前払いにあたる金額を繰延税金資産として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を減少させます。
逆に法人税等の未払いがある場合は法人税等の未払いにあたる金額を繰延税金負債として計上し、同時に法人税等調整額という勘定科目を使って法人税等の金額を増加させます。
ただし、損益を純資産に直入れする場合のように収益や費用に影響がない場合は、法人税等への影響もないので、法人税等調整額を使うことはありません。
- 弊社が運営している【簿記革命2級】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座-商業簿記2級」「暗記不要の簿記独学講座-工業簿記2級」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに簿記2級や簿記1級の合格を目指して勉強したい方は簿記2級通信講座【簿記革命2級】をご検討ください。
- 簿記2級を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記2級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法-簿記2級の勉強方法」で詳しく解説しています。
- 簿記2級の独学に向いたテキストについては「【日商簿記2級】独学向けおすすめテキスト8選【2022年版】」で詳しく解説しています。


コメント
はじめてコメントさせていただきます。
いつも勉強させていただいております、わかりやすい記事をありがとうございます。
税効果会計について理解するのに苦労していましたが、こちらの記事を読んで理解が進んだ気がします。
2点わからないことがあったので質問させてください。
1. 当期損金として認められなかった減価償却費でも、いずれ損金として認められていくというのはよくわかりました(減価償却できる金額の総額は会計上も税務上も同じだから)。
そしていずれ認められるという点で、繰延税金資産として処理することも理解しました。
対して、貸倒引当金の損金不算入金額は、いずれ損金として認められるとは言い切れないのでは、と思いました。
貸倒引当金の記事内の説明で、「この12,000円は実際に貸倒れが発生したときに税金の支払額が減少することで回収されます。」とありますが、貸倒れが発生しなければ税金の支払いが減少することはなく、繰延税金資産のまま残るという理解でよいでしょうか。
また、実際に貸倒れが発生したときの繰延税金資産等の処理についても参考までにお教えいただけないでしょうか。
2. その他有価証券について、評価差額は純資産に計上しているのに「評価差益のうち40%は将来税金として支払わなければならない」というのがよく理解できませんでした。
また、計上した繰延税金負債も翌期首にはなくすので、繰延税金負債は一時的に計上しただけで、複数会計期間に渡って影響するものではないということでしょうか。
そうするとやはり、「将来税金として支払わなければならない」というのがわからないです。
うまく説明できているかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。早速ご質問にお答えします。
>貸倒引当金の損金不算入金額は、いずれ損金として認められるとは言い切れないのでは、と思いました。
この部分についてですが、あくまでも決算時における予測(統計的な推計)だと考えます。そもそも貸倒引当金自体が「過去の数値にもとづく将来の予測(主観的なものではなく客観的なものである必要があります)」です。決算日においては将来いくら貸し倒れるかは分かりませんが、「過去の経験から〇〇円くらい貸し倒れると推計できる」という計算にもとづいて計上しています。税効果会計も同様に考え行うことになります。
実際に貸倒れが発生した場合の仕訳は「(借)法人税等調整額×××/(貸)繰延税金資産×××」となります。貸倒引当金がなくなったときにはこの仕訳を切ることになるので、仮にすべての売掛金や受取手形が回収されたとしても同様の仕訳を切ることになります(回収したときに切るのではなく、決算日の減価償却費の仕訳と相殺される形になります)。
>その他有価証券について、評価差額は純資産に計上しているのに「評価差益のうち40%は将来税金として支払わなければならない」というのがよく理解できませんでした。
「将来」というのは「その他有価証券を売却したとき」です。その他有価証券は売買目的ではありませんが、それでもやはり将来いずれ売却することが想定されています。その他有価証券を売却したときに利益が出ていれば、その利益の40%は税金として支払わなければならないので、その金額分は期末時点でも純資産ではなく負債であると考えます。
回答は以上です。参考にされてください。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
>仮にすべての売掛金や受取手形が回収されたとしても同様の仕訳を切る
この部分の認識が抜けてしまっておりました。
債権が無事すべて回収されたら貸倒引当金もなくなるので、いずれ「(借)法人税等調整額×××/(貸)繰延税金資産×××」の仕訳は切ることになるのですね。
その他有価証券については、期末時点で売却するとしたら、ということで時価評価に加えて一時的に金額の40%を負債として財務諸表に記載するのだと理解しました。(理解に相違があればご指摘いただけると嬉しいです…)
この度はお答えいただき誠にありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。げんさんの理解で合っています。お役に立てて何よりです。簿記の勉強、応援しています。