- 簿記を勉強していると諸口っていう言葉が出てくるんだけど……
- 諸口っていう言葉がいろいろなところで出てきて使い方がよく分からない
- 諸口について教えて!
簿記を勉強していると色々なところで諸口という言葉が出てきますが、諸口については詳しい説明はされないことが多く、とまどっている方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん諸口についても熟知しています。
この記事では諸口という言葉が使われる3つのケースについて解説します。
この記事を読めば諸口についてより深く理解できるので、不必要にとまどってしまうことがなくなります。
結論を一言で言うと、簿記における諸口には「相手勘定科目が複数のときに書く諸口」「特殊仕訳帳制にある特別欄以外の諸口欄」「仕訳の勘定科目が複数の場合に上の行に書く諸口」の3つがあります。
簿記での諸口の読み方は「しょくち」
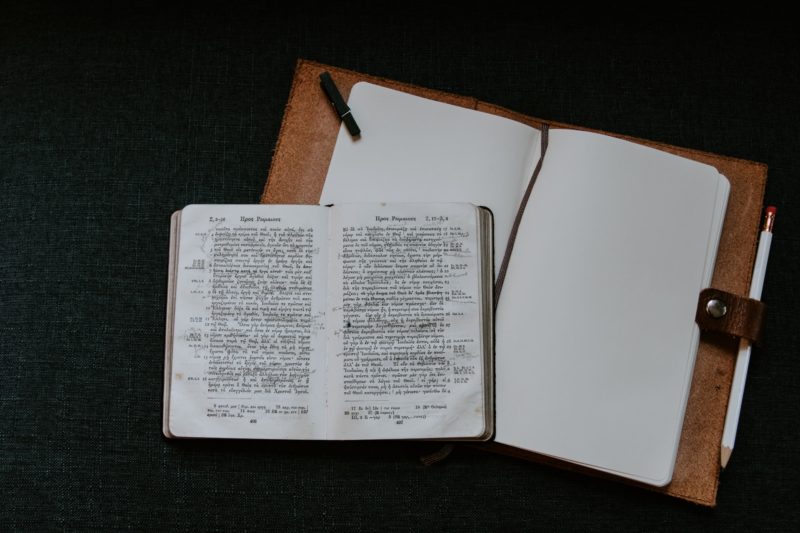
最初に諸口の読み方について解説します。簿記で諸口と出てきた場合は「しょくち」と読みます。
「地名」や「人名」の場合には諸口を「もろくち」「もろぐち」と読むことがありますが、簿記では「しょくち」としか読みません。
諸口とは【簿記での諸口の3つの意味と使い方】
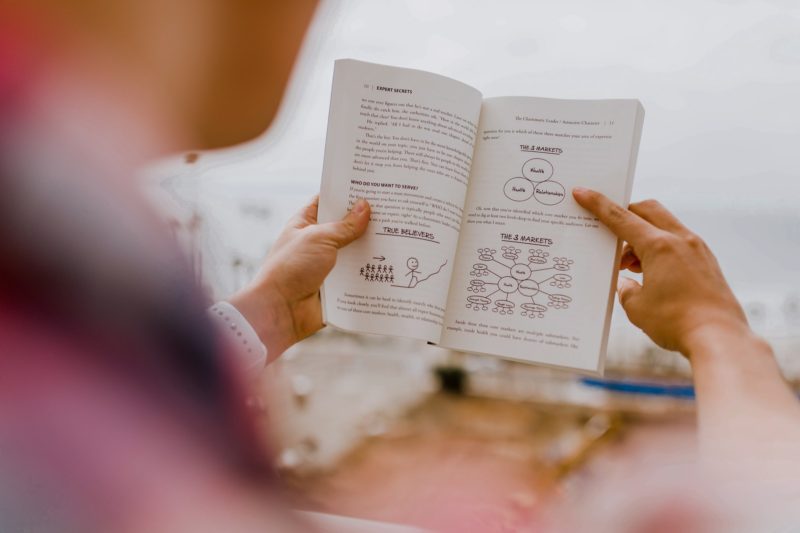
簿記で出てくる諸口は次の3つです。
- 勘定科目としての「諸口」
- 特殊仕訳帳制における「諸口」欄
- 仕訳帳の上の行に書く「諸口」
勘定科目としての「諸口」
仕訳帳から総勘定元帳へ転記するとき、相手勘定科目が複数のときには摘要欄に「諸口」と書きます。
仕訳帳から総勘定元帳への転記については「【簿記3級】総勘定元帳の書き方と転記のやり方」で詳しく解説しています。
例えば次の仕訳を総勘定元帳に転記したときには「売上」の総勘定元帳の摘要欄に諸口と書きます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 売掛金 | 100,000 200,000 | 売上 | 300,000 |
複数書き込むにはスペースが足りないからですが、内容を知りたいときには仕訳帳を見なければならないので不便です。
「現金・売掛金」のように書いた方が便利な気もしますが、実際は諸口と書きます。
特殊仕訳帳制における「諸口」欄
特殊仕訳帳制で特別欄を作った場合、特別欄以外の欄を「諸口」欄と言います。
特殊仕訳帳制については「特殊仕訳帳のやり方を問題例でわかりやすく【簿記論】」で詳しく解説しています。
諸口欄の諸口は「その他」という意味で使われています。
諸口欄は重要で、特殊仕訳帳制では必要不可欠なのですが、意味的には「その他」なのだから「その他」と書いた方が分かりやすい気がします。しかし、実際は諸口欄と書きます。
諸口という言葉は「諸(いろいろな)」「口(勘定口座)」という意味で昔は使われていたのですが、古語みたいになっているので、現在では意味が通じません。
より適切な意味を表す言葉に変わっていくことを個人的には希望しています。
仕訳帳の上の行に書く「諸口」
複合仕訳を仕訳帳に書く場合には上の行に「諸口」と書きます。ですが、完全に昔の話で今は書かないのが普通です。
「諸口」と書くことで、その下の仕訳は複合仕訳だと伝えることができるのですが、それだけです。諸口と書かれていなくても少し注意すれば複合仕訳だとわかります。
簿記的にも重要なことではないので、今は教わることはほとんどありません。
諸口は現在ではほとんど使わない

諸口という言葉は昔はよく使われましたが、現在ではほとんど使われません。
現在は会計帳簿を手書きで書くことがほとんどなくなったこと、特殊仕訳帳を使うことがほとんどなくなったことが大きな理由です。
かなり昔に発売された簿記・会計の書籍では見かけることがありますが、それ以外ではほとんど見ることはなくなっています。
【まとめ】諸口の意味とは【簿記での諸口の3つの使い方をわかりやすく】

簿記で出てくる諸口は次の3つです。
- 仕訳帳から総勘定元帳へ転記するとき、相手勘定科目が複数のときに摘要欄に書く「諸口」:スペースがないから諸口と書く
- 特殊仕訳帳制における特別欄以外の「諸口」欄:その他という意味で書かれる
- 勘定科目が複数の場合に上の行に書く「諸口」:勘定科目が複数であることを示すために書かれる
- 弊社が運営している【簿記革命】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに日商簿記の合格を目指して勉強したい方は【簿記革命】をご検討ください。
- 簿記を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法」で詳しく解説しています。


コメント