- 簿記の勉強をしていたら現金過不足っていう勘定科目が出てきたんだけど……
- 現金過不足の問題をどのように考えたら理解できるのか分からない
- 現金過不足という勘定科目についてわかりやすく教えて!
現金過不足は考え方が難しいので、どのように考えたらいいのか分からずに混乱してしまう方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん現金過不足についても熟知しています。
この記事では現金過不足という勘定科目の分類と現金過不足の仕訳の考え方についてわかりやすく解説します。
この記事を読めば現金過不足の考え方がより深く理解できるので、簿記3級の試験で現金過不足に関する問題が出題されても自信を持って解けるようになります。
結論を言うと、帳簿の現金残高と実際の現金残高にズレを発見したら、とりあえず現金過不足という勘定科目を使って帳簿の現金残高を実際の現金残高に合わせておきます。
そして、帳簿の現金残高と実際の現金残高のズレの原因が分かったら、そのときに改めて正確な処理をします。
「現金過不足」という勘定科目は資産・負債・資本・収益・費用のどれにもあてはまらない勘定科目です。借方にある時は費用の勘定科目、貸方にある時は収益の勘定科目と考えるとうまくいきます。
現金過不足:現金残高の帳簿と実際のズレを処理する勘定科目

現実では、帳簿に書いてある現金の金額と実際にそこにある現金の金額が一致しないことがあります。
実際の現金が足りないからと言って、自分の財布からお金を足したりしてはいけません。実際の現金が余っているからと言って、自分のポケットに入れてももちろんいけません。
帳簿上の現金と実際の現金が一致しないときには現金過不足という勘定科目を使って会計処理を行います。
実際の現金残高と帳簿の現金残高が一致しない3つの原因

なぜ帳簿の現金残高と実際の現金残高の不一致が起こるのでしょうか。完璧に取引が行われ、帳簿が完璧に記帳されていればこのようなことは起こりません。
不一致が起こったということはどこかにミスがあったということです。
具体的には次のようなミスが考えられます。
- 現金の紛失
- 記入ミス
- お釣りの渡し間違い
ミスは人間が関わっている限りゼロにはできません。そこで、このようなミスが起こった場合の処理の仕方を決めておく必要があります。
現金以外に不一致が発生した場合はどうなるのでしょう。このように考えている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、現金以外の不一致の場合は、不一致がなくなるまで原因を突き止めます。取引の相手方から書類を取り寄せたり、領収書と照合したりして徹底的に一致させます。
当座預金の不一致は、銀行に残高を問い合わせて帳簿と突き合わせます。
売掛金や買掛金も相手先に問い合わせて不一致の原因を突き止めます。原因が分かれば相応の仕訳を切ることができます。
ではなぜ、現金だけが特別扱いなのでしょう。現金に関しては、徹底的な照合が不可能なことが多いのです。
現金をただ紛失した場合、紛失額を徹底的に突き止めることは不可能です。お釣りの渡し間違いの額を突き止めることも不可能です。
相手の方が申し出てくれることもあるかもしれませんが、そもそも相手も気づかない場合も多いでしょう。
このように、現金の不一致は原因を徹底的に突き止めることができないことが多いのです。
当座預金の不一致を調査するときに使う表を銀行勘定調整表といいます。現金勘定調整表については詳しくは簿記2級で学習します。
実際の現金残高と帳簿の現金残高が一致しない場合の会計処理

原因が分からなければ適切な仕訳を切ることができません。そこで『現金過不足』という勘定科目を使って一時的に処理をしておきます。
『現金過不足』という勘定科目を使って、帳簿の現金残高を実際の現金残高に合わせておくのです。
現金過不足で処理するときに気をつけて欲しいのが、必ず帳簿を実際に合わせるということです。「実際を帳簿に」ではありません。「帳簿を実際に」です。
そもそも簿記の目的は企業の財政状態及び経営成績を明らかにすることでした。現金残高は「実際」にそこにある金額でなければ正しく財政状態を明らかにしているとはいえません。
ありもしない現金が帳簿に記載されていたり、あるはずの現金が帳簿に記載されていなかったりしてはいけないのです。そのため、「帳簿を実際に」合わせるのです。
現金過不足の仕訳問題の具体例

現金過不足の仕訳について具体例で考えてみましょう。
1.不一致の発生
5月31日、総勘定元帳の現金勘定を締めてみると残高は50,000円でした。ところが、手元の金庫を見ると現金は30,000円しかありません。会社内で色々と調べてみましたが、原因は不明でした。
この例題の仕訳を考えてみましょう。帳簿が50,000円、実際は30,000円しかありません。実際の方が20,000円少ないわけです。
そこで、帳簿を実際に合わせるために帳簿の現金を20,000円減らさなければいけません。現金は資産であり、減少は貸方に書きます。よって、『(貸)現金20,000円』となります。
問題は借方です。原因が不明なため正確な借方の勘定科目は決められません。そこで、『現金過不足』という勘定科目を使います。
現金過不足という勘定科目は借方にあるときには費用になります。
20,000円現金が少ないということは、20,000円損したと考えます。費用の発生と考えて借方に現金過不足という勘定科目を使います。よって『(借)現金過不足20,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金過不足 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
2.決算整理仕訳(現金過不足の原因が判明した仕訳)
12月31日、決算のためにそれぞれの勘定の確認をしていました。その際、A社に対する買掛金の残りが80,000円と帳簿にあったため、本当に合っているのかA社に確認しました。
当社「当社のA社に対する買掛金の残高は80,000円ですよね?」
A社「いいえ、御社に対する売掛金(当社から見たら買掛金)の残高は65,000円ですよ。」
そこで、お互いの帳簿を突き合わせて確認したところ、どうやら当社が5月20日に買掛金を15,000円現金で払っていたのに記帳を忘れてしまっていたと分かりました。
この例題の仕訳を考えてみましょう。帳簿では買掛金の残高は80,000円でしたが、実際には65,000円しかありませんでした。
ここでも帳簿を現実に合わせます。実際の方が買掛金は15,000円少ないので、帳簿の買掛金を15,000円減らさなければなりません。
買掛金は負債であり、減少は借方に書きます。よって『(借)買掛金15,000円』となります。
問題は貸方です。現金で支払っているので現金としたいところですが、貸方は現金にはなりません。
5月31日に現金の勘定は実際に合わせています。5月31日に現金は原因不明なまま20,000円減少させているのです。
足りなかった現金20,000円のうち、15,000円分の原因がいま分かったのです。
5月31日に現金を減らしているのに、もう一度現金を減らしてしまっては二重で現金を減少させることになってしまいます。
あくまでも12月31日には原因が分かっただけです。現金は5月31日にすでに減らしています。
ここで減らすのは『現金過不足』です。20,000円の原因不明の現金の減少を費用(損失)として処理していたところ、費用(損失)ではなく、負債である買掛金の減少だと分かったのです。
費用である『現金過不足』のうちの15,000円分を減らして、負債である『買掛金』を15,000円分減らすことになります。『(貸)現金過不足15,000円』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 15,000 | 現金過不足 | 15,000 |
3.決算整理仕訳(現金過不足の原因が判明しなかった仕訳)
現金過不足がまだ5,000円分残っていますが、原因が分からないままです。これ以上調べても原因は突き止められそうにありません。
しかし、原因不明である『現金過不足』という勘定科目を貸借対照表に残すのは格好がつきません。ここでも仕訳を行います。
現金過不足が費用の場合、つまり借方に残っている場合は雑損という勘定科目に振り替えます。
つまり、現金過不足(費用)をなくして、代わりに雑損(費用)にするのです。
まず費用である現金過不足を減らします。費用の減少は貸方に記入するので『(貸)現金過不足5,000』となります。
次に費用である雑損を増やします。費用の発生は借方に記入するので『(借)雑損5,000』となります。
まとめると次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑損 | 5,000 | 現金過不足 | 5,000 |
ここまでの仕訳をまとめて書くと次のようになります。
| 取引 | 仕訳 | 現金過不足残高 |
|---|---|---|
| 不一致の発生 | (借)現金過不足 20,000/(貸)現金 20,000 | 借方20,000円 |
| 決算その1 | (借)買掛金 15,000/(貸)現金過不足 15,000 | 借方5,000円 |
| 決算その2 | (借)雑損 5,000/(貸)現金過不足 5,000 | 残高なし |
現金過不足の勘定の動きを取引と仕訳の両面からイメージしておくことが重要です。現金過不足の残高は不一致額の残高です。
そして、決算まで残ってしまった現金過不足に関しては雑損(または雑益)に振り替えます。
ちなみに、2つの決算整理仕訳を1つの仕訳で行うことも一般的です。その場合の仕訳は次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 雑損 | 15,000 5,000 | 現金過不足 | 20,000 |
また、決算時に不一致が分かった場合は「不一致の発生」もまとめて1つの仕訳にします。その場合の仕訳は次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 雑損 | 15,000 5,000 | 現金 | 20,000 |
3つの仕訳を並べて書き、借方と貸方の両方で出てくる勘定を同じ金額分だけ相殺すると考えると分かりやすいです。
この場合、『現金過不足20,000』が貸借両方に出てくるので相殺することになります。
【まとめ】現金過不足という勘定科目と仕訳をわかりやすく
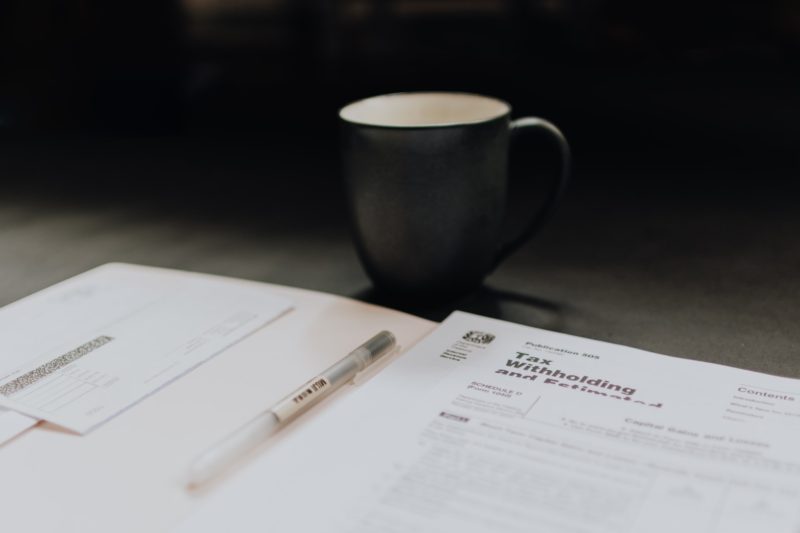
帳簿上の現金と実際の現金が一致しないときには現金過不足という勘定科目を使って処理を行います。帳簿上の現金と実際の現金の違いを合わせるときは必ず「帳簿」を「実際」に合わせます。
「現金過不足」という勘定科目は資産・負債・資本・収益・費用のどれにもあてはまらない勘定科目です。
決算まで残った現金過不足勘定は「雑損」または「雑益」に振り替えます。
- 弊社が運営している【簿記革命3級】は、当サイト「暗記不要の簿記独学講座-簿記3級」を大幅に加筆修正したテキストと、テキストに完全対応した問題集がセットの通信講座です。私とともに簿記3級の合格を目指して勉強したい方は簿記3級通信講座【簿記革命3級】をご検討ください。
- 簿記3級を効果的に身につけるためには、効果的な勉強方法で勉強することが大切です。簿記3級の勉強法については「簿記1級にラクラク受かる勉強法-簿記3級」で詳しく解説しています。
- 簿記3級の独学に向いたテキストについては「【2021年版】独学向け簿記3級おすすめテキスト【9つのテキストを徹底比較】」で詳しく解説しています。


コメント
重箱の隅をつつくようですが…
当社「当社のA社に対する買掛金の残高は80,000円ですよね?」
A社「いいえ、買掛金の残高は65,000円ですよ。」
とありますが、A社回答で「売掛金の残高」としないのは不自然ではないでしょうか。
じんちゃんさん
コメントありがとうございます。確かにそうですね。補足しておきます。ご指摘ありがとうございます。